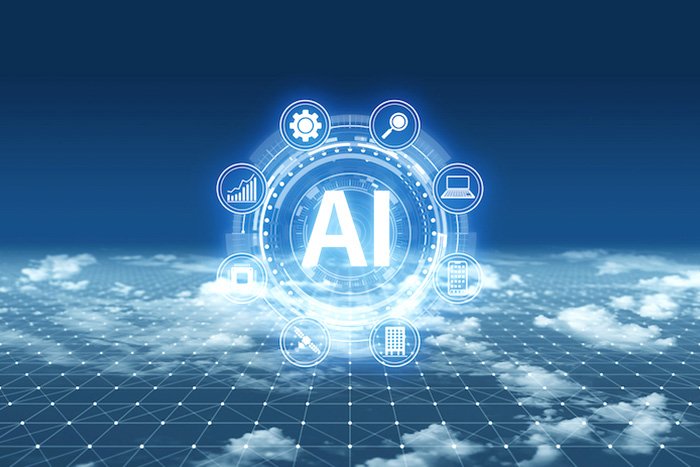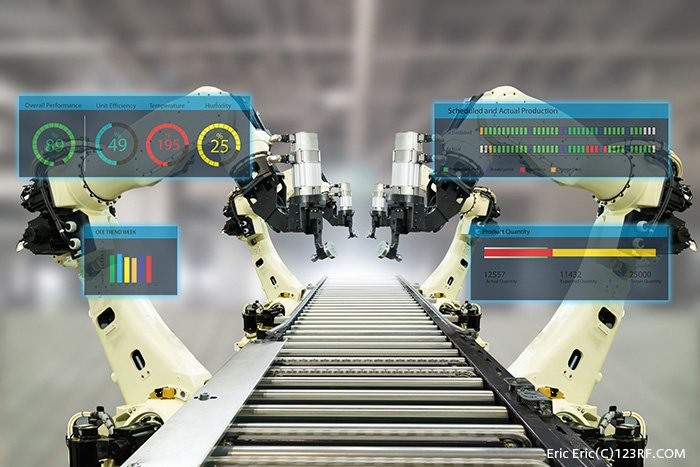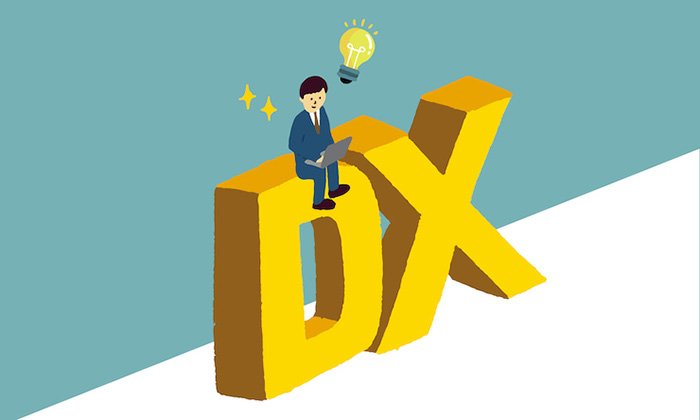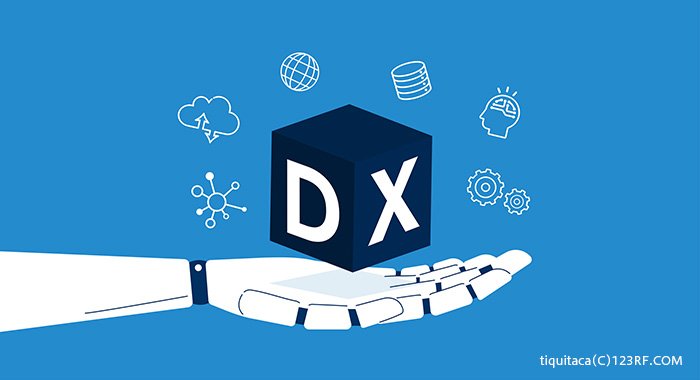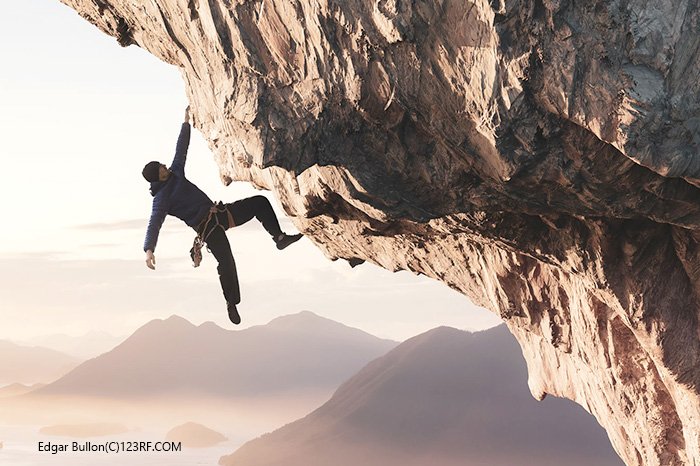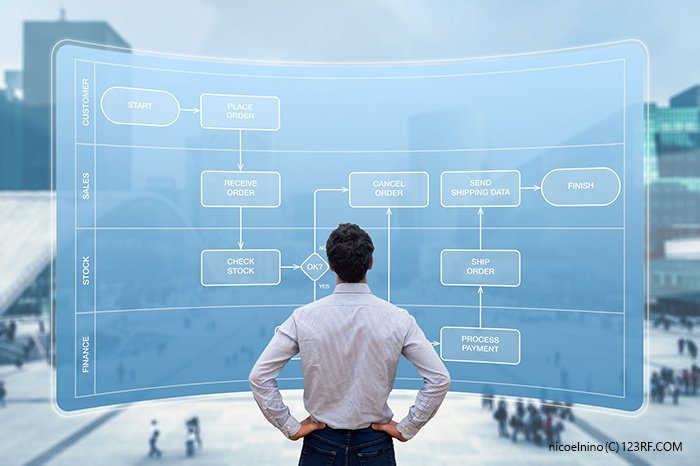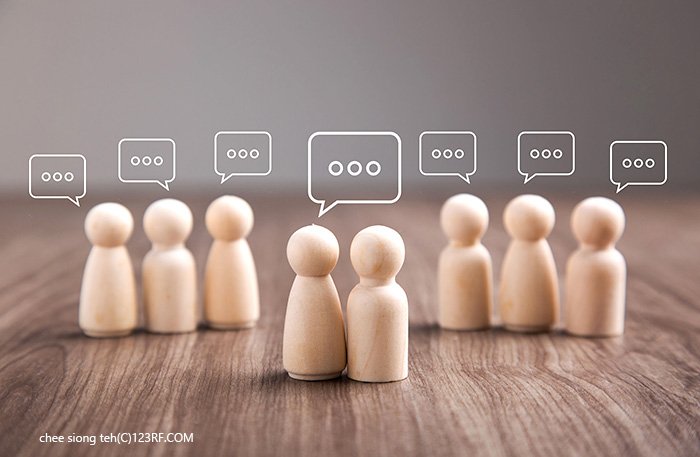EBPMの成功事例~自治体による最新の取り組みと政策の進め方を紹介~

EBPM(Evidence Based Policy Making)は、データやエビデンスを活用して政策を設計・実行するアプローチです。少子高齢化や災害対策、地域活性化といった社会課題が深刻化する中で、多くの自治体から注目を集めています。
本記事では、EBPMの成功事例を7つ紹介するとともに、よく使われる手法や進め方も解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
また、EBPMは、各自治体で進められているスマートシティ構想の核としても注目されています。インテックではスマートシティの進め方に関する資料もご用意しております。以下より「スマートシティの進め方ガイドブック」もご活用ください。
※その他、スマートシティの事例集や関連資料は<こちら>からダウンロードしていただけます。
EBPMとは

EBPM(Evidence Based Policy Making)とは、エビデンス(根拠)に基づく政策立案のことです。
政策を立案・実行する際には、まず目的を明確にし、その政策で目的が達成できる見込みがあるかを考える必要があります。さらに実施後に目的が実際に達成されたかを検証しなければなりません。
EBPMを活用すれば、経験や勘に頼らず、客観的なエビデンスを根拠として政策を決定・遂行できます。これにより政策の効果を合理的に判断し、より効果的な行政運営と、信頼性の向上を実現することが可能です。
近年ではスマートシティの実現に向けた施策が各自治体でおこなわれていますが、EBPMはその取り組みにおいても重要な役割を担っています。
*スマートシティの構想について、こちら↓の記事もあわせてご覧ください。
関連記事 未来のまちづくりを支えるスマートシティの構想とは?
EBPMが注目されている背景

EBPMは、社会課題が複雑化・多様化する現代において、政策の有効性と効率性を高める手法として注目を集めています。ここでは、注目されている背景を見ていきましょう。
自治体を取り巻く環境の変化
近年、自治体は外部環境と内部環境の双方で大きな変化に直面しています。人口減少や高齢化といった外的要因に加え、職員数や財源の不足などの内部的課題も重なっているのが現状です。自治体では、限られた行政資源をいかに効率的に活用するかが重要なテーマとなっています。
外的環境
日本における大きな課題の一つが、少子高齢化や過疎化による人的資源の減少です。こうした状況下では、従来の慣例や経験則に基づいた政策立案では効率的な行政運営を維持することが難しくなります。
特に医療・福祉・インフラ整備といった分野は財政負担が大きいため、費用対効果を見極めた予算配分が欠かせません。そこで注目されているのがEBPMです。
統計データや調査結果などの客観的根拠に基づいて施策を検討することで、無駄な支出を抑え、限られた財源を最大限に活用することが可能です。持続可能かつ実効性のある政策を実現できるでしょう。
内的環境
一方、自治体内部では、職員数の減少による人手不足が深刻化し、業務遂行に支障をきたすケースが見られます。以下のような課題が複合的に存在しているのが現状です。
- 保守的な組織風土や新しい発想を取り入れる柔軟性の不足
- 厳しい財政見通し
- 成果を正しく測定できない評価システムの不備
こうした状況に対応するには、限られた行政資源を効率的に活用し、地域課題に迅速かつ的確に対応できる仕組みを整えることが欠かせません。EBPMは合理的な対応策を講じるための有効な手段になります。
ICT(情報通信技術)の発展とビッグデータ活用の可能性
近年はICTの急速な発展により、行政や民間が保有する膨大なデータを収集・保存・分析するための環境が整備されています。インターネットの高速化やクラウドサービスの普及、AIや機械学習の進歩により、これまで膨大な人手や時間を必要としていたデータ処理・分析を短時間で高精度に実施できるようになりました。
自治体においても、国勢調査や各種統計データに加え、センサーやIoT機器から得られるリアルタイムデータを組み合わせ、活用できる体制が整備されています。たとえば、交通量データを用いた防災計画や、高齢化率と医療データを組み合わせた地域医療体制の強化といった実践的な活用が進んでいます。
こうした技術基盤の整備は、データに基づく迅速かつ的確な政策立案を可能にし、EBPMの実現を後押しするでしょう。
政府による取り組みの推進
EBPMの普及を全国的に後押ししているのが、政府の取り組みです。内閣府は「統計改革推進会議最終とりまとめ」(2017年5月)を公表し、政策課題を迅速かつ正確に把握し、有効な対応策を選択・検証する必要性を明確に示しました。
内閣府はEBPMの枠組みに基づき、政策効果の測定に不可欠な統計や各種データを活用して政策を立案しています。政策の有効性を高めるとともに、行政に対する国民の信頼確保を目指しています。
現在、こうした政策を展開しているのは国だけではありません。地方公共団体にも導入が広がり、データを根拠とした政策実行が主流になりつつあります。政府は「EBPM推進委員会」を設置して政府全体での推進体制を構築するとともに、EBPMを普及・浸透させるための基本解説書「EBPMガイドブック」を公開するなど、各自治体がEBPMを実践しやすい環境整備を進めています。
これは、従来の経験や慣習に依存した手法から、科学的根拠に基づく合理的な政策立案へと転換していることを示す動きと考えられます。
EBPMの成功事例7選
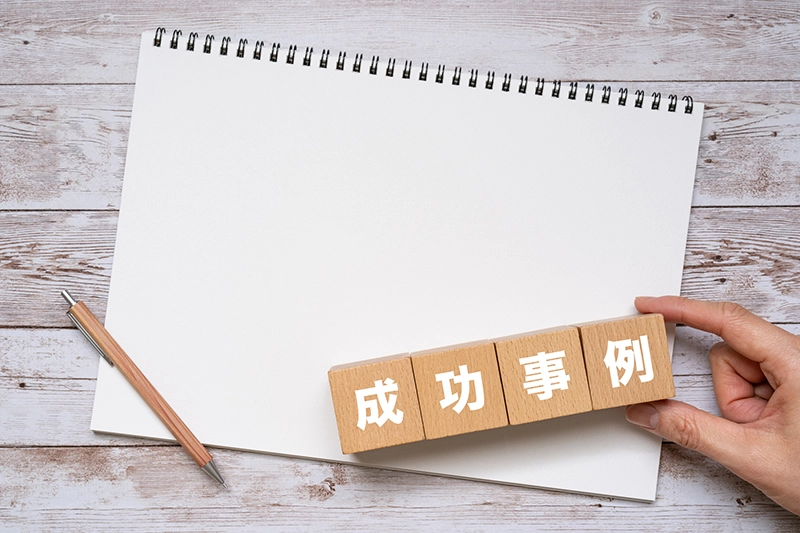
近年、多くの自治体がEBPMを進め、地域の課題解決につなげています。ここでは、国内における成功事例を7つ紹介します。
自分たちの地域に合った施策のヒントを得られるよう、ぜひ参考にしてみてください。
【兵庫県神戸市】職員が分析・可視化された複数のデータを一覧できるダッシュボード「神戸データラウンジ」を公開
兵庫県神戸市では、行政データを活用した政策立案を進めるためにBIツールを用いたダッシュボード「神戸データラウンジ」を構築し、職員向けに公開しました。この仕組みにより、各基幹系システムから抽出・加工されたデータを視覚的に可視化でき、職員自身が分析を実施して政策立案に活用できるようになっています。
さらに、データ入手や資料作成にかかる時間が短縮され、職員は政策議論により多くの時間を割けるようになりました。また、データ分析に不慣れな職員でも操作できるため、外部委託に頼らずに分析できるようになった点も大きな成果です。
この取り組みは高く評価され、総務省主催の「Data StaRt Award」において、2022年には総務大臣賞、2023年には特別賞を受賞しました。市民向けには、神戸市役所の公式サイト内にある「神戸データラボ」を通じて公開データの活用も進めています。
【兵庫県加古川市】駅前再開発における移動データ活用
兵庫県加古川市は、2000年代以降、行政評価のツールとしてロジックモデルを活用してきた自治体の一つです。
人口減少や少子高齢化が進む中で、同市はJR加古川駅周辺への都市機能の集積と公共交通ネットワークとの連携により、持続可能な都市構造への転換を目指しました。このプロジェクトの主な目的は、以下の2つです。
- 駅前を訪れる人々の行動実態を把握し、今後の施策立案の基礎データとすること
- 市立図書館の駅前商業施設への移転前後の利用者変化を把握し、移転効果を可視化すること
取り組みの中で「駅前に商業施設を配置するだけでは交通手段の変化にはつながらない」という課題が明らかになり、実際に駅周辺を車で訪れる人が6割にのぼることがデータで示されました。また、分析結果はオンライン市民参加ツール「デシディム(Decidim)」で公開され、市民からの意見やアイデアを募ることで共創型のまちづくりの推進にもつながっています。
さらに、人の流れが活発なエリアや曜日・時間帯ごとの行動パターンを地図上で把握できるようになった点も本プロジェクトの大きな成果です。これを基に、駅前中心市街地の活性化と公共交通利用促進の両面を捉えた施策検討が進められています。
【高知県】「Society5.0型農業」で収量増加・品質向上を実現
高知県では、農家ごとの栽培管理方法が属人的で収量や品質にばらつきがあり、さらに若手農家への技術継承が難しいという課題を抱えていました。
そこで、産学官が連携し、営農に必要なデータや情報を一元的に集約・共有・活用できる「IoPクラウド(SAWACHI)」を構築しました。この事例では、県知事と1,420戸の農家との間で「データ利用契約」を締結し、データ収集・蓄積・共有・活用体制を整備した点もポイントです。
さらに、令和5年度にSAWACHI利用農家と未利用農家の年間出荷量を比較したところ、SAWACHI利用農家の方が約3割高いことが確認されました。統計データとリアルタイムデータを組み合わせて活用できる環境を整備したことにより、収量の増加と品質の向上を実現した好例です。
【宮城県仙台市】データ活用を促進して消防と医療機関の連携を強化
宮城県仙台市では、コロナ禍で救急医療が逼迫する中、消防と医療機関の連携強化が急務となっていました。しかし、当初は意見交換の場で救急搬送の受け入れを依頼していたものの、具体的なデータを示さなかったため改善につながらない課題を抱えていました。
そこで導入をしたのが、救急統計データから応需率を算出し、週次でモニタリングする仕組みです。これにより、救急医療の逼迫を示す兆候を早期に把握できるようになりました。
応需率(救急車の受け入れ率)が低下する複数のパターンが明らかになり、新たな課題の発見にも結びついています。
さらに、データを根拠に医療機関と意見交換を実施した結果、救急搬送の受け入れ体制拡充に向けた実効性のある対策が講じられ、応需率の改善も確認されました。現在では、コロナ禍以降も持続可能な救急医療体制を検討・実施する取り組みが進められており、地域医療の安定化につながっています。
【栃木県宇都宮市】カープローブデータを収集して潜在的な危険箇所を可視化
栃木県宇都宮市では、通信機能付きICタグを活用し、急ブレーキ・急加速・急ハンドル・速度超過といったカープローブデータを収集しました。収集したデータは、交通事故発生状況をメッシュの色で示すヒートマップやスタックチャートとして可視化され、潜在的な危険箇所の抽出に役立てられています。
さらに、可視化したマップを用いた報告会を開催し、地域住民が主体となって「まち歩き(危険箇所の現地確認)」や「対策検討会」を実施しました。その結果、潜在的な危険箇所に対して地域の理解と協力を得ながら、看板設置(ソフト対策)やハンプ設置(ハード対策)などを進めています。
今後は、地域や行政、警察等を連携し、ソフト・ハードの両面から地域の実情に応じた交通安全対策を実践する方針です。
【栃木県真岡市】3C分析でHPやSNSの内容を改善、サイト訪問数が3倍に
栃木県真岡市は、市の特産品であるいちごの認知度向上を目的にプロモーション施策を検討していました。当初は効果的な情報発信に必要な環境やデータが整備されていないという課題を抱えていました。
そこで、市は3C分析を用いてイチゴプロモーションの戦略を立案し、HPやSNSの掲載内容や投稿内容を改善する取り組みを始めることになります。
さらに、市が保有するWebサイトやSNSなど、すべてのデジタルツールの表示回数、クリック数といったデータを数値化し、ダッシュボードで一元的に蓄積していきました。そのデータを基に仮説を立て、投稿内容の見直し、実行、分析というPDCAサイクルを繰り返し実施しています。
この結果、特設サイトの訪問数は約3倍、観光いちご園の利用者数も1.5倍に拡大し、ふるさと納税の返礼品として提供されるいちごの申込件数は20倍にまで増加しました。
真岡市は、デジタルマーケティングの推進を通じて市の魅力を効果的に発信し、いちごブランドのさらなる認知度向上を目指しています。
【岐阜県関市】予測モデルを作成し、信頼性の高いデータを政策検討に活用
岐阜県関市では、人口減少が加速する中、少子化対策として子育て世代への支援が欠かせない取り組みと考えられてきました。しかし、現行制度の予算規模が膨大で、年齢要件を拡大した際にどの程度のコストがかかるのかが不透明だったため、長らく実現には至っていませんでした。
年齢要件の引き上げを再検討するにあたり、将来的に発生するコストを算出するための予測モデルを作成することになります。市独自の人口推計に助成額予測係数を掛け合わせ、18歳までを対象とした場合のモデルを構築しました。これにより、信頼性の高いデータをもとに政策を検討できる体制を整備しました。
また、検証の結果、2023年度における16歳〜18歳の医療費助成実績(概算値)と推計値の差は誤差がプラスマイナス5%以内に収まり、精度の高い予測であることが示されています。
*スマートシティの実現に向けて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。
※その他のスマートシティ関連資料、お役立ち資料は<こちら>をご覧ください。
EBPMでよく使われる手法4選

EBPMを進める際には、さまざまな分析手法が活用されます。代表的な手法が、以下の4つです。
- ロジックモデル
- ランダム化比較実験
- 回帰不連続デザイン(RDD)
- 差の差分析(DID)
ここでは、それぞれの概要や特徴を見ていきましょう。
ロジックモデル
ロジックモデルとは、施策の目的・手段・成果などを体系的に整理する手法です。ロジックモデルの構成要素とフローをまとめましたのでご覧ください。

-
1. 現状・問題:前提となる背景事情や解決したい社会問題
-
2. 要因分析・課題設定:ボトルネックの分析、解決すべき課題
-
3. インプット:事業を実施するために投入される資源(予算、人員、施設など)
-
4. アクティビティ:投入された資源を用いて行われる具体的な政策内容
-
5. アウトプット:政策手段による活動目標・実績
-
6. 初期アウトカム:アウトプットによってもたらされる成果や変化(直接的)
-
7. 中期アウトカム:アウトプットによってもたらされる成果や変化(他の影響も含む=複合的)
-
8. 長期アウトカム:アウトプットによってもたらされる成果や変化(他の影響も含む=複合的)
-
9. インパクト:あるべき姿や最終的に目指すべき姿、国民・社会への社会的な影響
上記の項目に沿って施策を設計すれば、目的と手段、そして成果のつながりが明確になり、効果検証や改善がしやすくなるでしょう。特にEBPMでは、こうした構造化によって施策の効果を定量的・客観的に評価する基盤を整備することが重要です。
ランダム化比較実験
ランダム化比較実験(RCT=Randomized Controlled Trial)とは、施策の効果を定量的に検証する手法です。対象者をランダムに二つのグループに分け、それぞれの成果指標を比較することで、因果関係を明確にでき、信頼性の高いエビデンスを得られます。
行政施策では実施が難しい場合もありますが、その際には行政区の境界付近で新たな施策を試行し、隣接する自治体や対象外地域と比較する方法が有効です。こうしたランダム化比較実験の仕組みを活用すれば、従来の経験や直感に頼らない科学的な政策判断が可能となります。
回帰不連続デザイン(RDD)
回帰不連続デザイン(RDD=Regression Discontinuity Design)とは、施策の対象者と非対象者を一つの基準(閾値)で分け、その前後のデータを比較する手法です。閾値付近の人々は属性や条件がほぼ同じであるため、ランダム化比較実験が行えない状況でも因果関係を推定しやすいメリットがあります。
たとえば、政策導入の基準として年齢や所得水準、試験点数など明確な線引きがあるケースで有効です。回帰不連続デザインは、信頼性の高いエビデンスを得る手段として注目されています。
差の差分析(DID)
差の差分析(DID=Difference in Differences)とは、施策対象者と非対象者それぞれの施策実施の前後のデータを分析する手法です。
時系列での変化とグループ間の差を同時に捉えられるため、単純な比較では排除できない外的要因の影響を軽減できます。これにより、政策や施策の効果をより正確に把握することが可能です。
EBPMの進め方

EBPMは、以下の4ステップで進めるのが一般的です。
- 解決すべき課題を明確にする
- 必要なデータを収集・分析する
- 政策を立案・実行する
- 実行した政策の効果を評価する
それぞれのポイントを見ていきましょう。
解決すべき課題を明確にする
EBPMの第一歩は、地域や社会に存在する課題を具体的に特定することです。統計データや住民アンケート、ヒアリングなどを通じて現状を把握し、解決すべき問題を明らかにしましょう。
その際には「少子化対策を進める」ではなく「出生率を◯%改善する」といった形で具体的かつ測定可能な課題を設定することがポイントです。課題を明確にすることで、後続のデータ収集や政策立案を効率的に進められます。
必要なデータを収集・分析する
続いて、課題を深く理解するために関連データを幅広く収集・分析しましょう。たとえば、人口統計や経済データ、地域ごとの比較事例などを整理し、分析することで、課題の本質を理解しやすくなります。
データを分析する際は、データの出典や信頼性を確認することも重要です。誤ったデータに基づいた政策は、失敗につながります。
EBPMを進める際は、精度の高いデータを活用することが成功のポイントになります。
政策を立案・実行する
次に、整理したデータを基にして解決策となる政策を設計しましょう。前項で紹介したロジックモデルを活用することで、目標や手段、期待される結果などを明確にできます。
政策を実行する際はKPI(Key Performance Indicator=重要業績評価指標)を設定し、数値で成果を測定できる仕組みを整えることが欠かせません。KPIを設定することで、政策の進捗や成果を客観的に把握でき、必要に応じて迅速な修正や改善につなげられます。
実行した政策の効果を評価する
政策を実行した後は、あらかじめ設定したKPIを使って成果を評価します。
期待通りの結果が出たかを確認し、達成できなかった場合は原因を分析して改善策を検討することが重要です。評価のプロセスは透明性を持って関係者と共有することで、次の施策に反映すべき改善点が明確になるでしょう。
こうした改善の積み重ねによって、より精度の高い政策立案を継続的に進められる体制が整います。EBPMを成功に導くためには、一度きりで終わらせるのではなく、改善サイクルを繰り返し回していくことがポイントです。
インテックのEBPM推進のサポート事例

インテックは、自治体のEBPM推進に向けたデータ活用基盤の整備からBIツール導入まで、一貫したサポートを提供しています。自治体職員や住民が自らデータを活用できる仕組みを構築できるのが強みです。
ここでは、インテックによるEBPM推進のサポート実績を2つ紹介します。
【羽咋市】データ連携基盤を整備し、スマートシティ実現を目指す土台作りをサポート
羽咋市は、スマートシティの実現に向けてEBPMの推進を検討し、職員だけでなく住民もデータを有効活用できる仕組みづくりを目指しました。インテックのアドバイスを受け、気象情報や監視カメラ、道路情報、公共施設や避難所の一覧といった多様なデータをダッシュボードに集約し、可視化を実現しています。
集約した情報は「データ公開サイト」として羽咋市のホームページで一般公開されており、誰もが活用することが可能です。これにより、小規模自治体ならではのEBPM推進とスマートシティの実現に向けた基盤が整いました。
さらに、児童の登下校見守り事業で得られた通学路ごとの通行量や、市内道路の危険箇所を把握するデータなどをデータ連携基盤に追加し、市民の安心・安全な暮らしの向上を図っています。
関連記事 インテック、石川県羽咋市のスマートシティデータ連携基盤を構築し、行政の効率化を支援 ~積雪監視や防災など
【富山市】BIダッシュボードの作成・活用をサポートし、まちづくりの進捗を把握できる体制を構築
富山市の事例を見ていきましょう。富山市は、人口減少や超高齢社会の進行を見据え、デジタル技術とデータ利活用によるスマートシティ政策を推進しています。
職員が自らデータ加工や分析、レポート作成を実施できるように、BIツールの「Tableau」を導入し、インテックがBIダッシュボードの作成と活用に向けた支援を実施しました。
富山市の都市計画課では、人口動態データをもとに年代ごとの人口や世帯分布を可視化し、市内の居住状況を視覚的に把握できるようになっています。これにより、富山市が進める「コンパクトなまちづくり」の進捗状況を的確に把握でき、データに基づく政策立案を後押しする体制が整いました。
関連記事 インテック、富山市のBIツール構築とデータ利活用を支援しデータの可視化や職員の技術習得をサポート
*スマートシティの実現に向けて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。
※その他のスマートシティ関連資料、お役立ち資料は<こちら>をご覧ください。
まとめ:EBPMの成功事例を参考にして効果的な施策を立案しよう

EBPMは、データやエビデンスに基づいて政策を立案・実行・評価することで、限られた資源を最大限に活かし、成果を高められる手法です。社会課題が複雑化・多様化する現代において、政策の有効性と効率性を高める手法として注目を集めています。
EBPMは、以下の4ステップで進めるのが一般的です。
-
1. 解決すべき課題を明確にする
-
2. 必要なデータを収集・分析する
-
3. 政策を立案・実行する
-
4. 実行した政策の効果を評価する
EBPMを成功させるためには、一度きりで終わらせるのではなく、改善サイクルを繰り返し回すことが欠かせません。今回紹介した事例を参考にしながら、施策の設計や改善に役立ててください。
インテックでは、さまざまな分野でICT技術を応用した独自のサービスを提供し、お客さまの事業展開を支えています。弊社のサービスについて詳しく知りたい方は、ぜひ「お問い合わせ」からご連絡ください。
*インテックが提供する「エリアデータ利活用サービス」の詳細はこちら↓のページをご覧ください
サービス紹介 エリアデータ利活用サービス
公開日 2025年10月16日
資料ダウンロード
-
【自治体の担当者必見!】失敗しない!スマートシティの進め方ガイドブック
本書はスマートシティの取り組みを推進するための進め方やコツについて解説するeBookです。 スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。

-
エリアデータ利活用サービス『事例集2025』『事例集2024』
2025年・2024年の事例集2冊をまとめてダウンロードしていただけます。
本書ではスマートシティの実現を目指すお客様に向けて、課題解決や取り組みに関する具体的な事例を多数紹介しています。スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。
-
エリアデータ利活用サービス紹介資料
スマートシティの実現を目指すお客様に向けて、データ連携基盤・都市OSの必要性やメリット、オープンデータの活用、各自治体での取り組み事例を紹介しております。
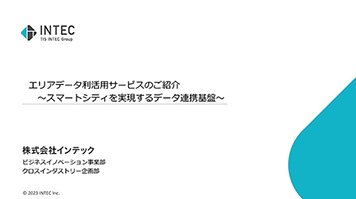
お問い合わせ
Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム
関連する商品・サービス
- エリアデータ利活用サービス
- IoTによるリアルタイムデータやオープンデータなど様々なサービス・ソリューションと連携し、地域の暮らしに関連するデータを収集・可視化・利活用を促進するデータ連携基盤を中心としたサービスです。
- 学校給食費・学校徴収金管理サービス らくらく集金
- らくらく集金は、給食費や教材費などの徴収管理業務を効率化し、利用者様の作業負担軽減を実現する自治体様向けサービスです。
- IaaS型クラウドサービス for IBM i(ASクラウドサービス)
- IBM Power System-iを利用し、仮想インフラを提供するIaaS型ホスティングサービスです。
- 生産管理パッケージ導入サービス(mcframe)
- 導入実績No.1の経験に基づき、製造業向け基幹サービスをご提供します。
- クラウド型経費精算システム(Spendia)販売代理パートナー
- 交通費、出張旅費、交際費など、経費精算に関わるすべての処理をオンライン上で完結できるクラウド型の経費精算システムです。
- クラウドHEMSサービス
- クラウド型でHEMSサービスを提供する、事業者向けのプラットフォームです。普段お使いのテレビがZEHに貢献するHEMSコントローラーになります。
- 地域農業情報活用支援システム
- 地域農業再生協議会さまの事務推進を強力にサポートするASPサービスを提供します。
- fcube 預り物件管理サービス
- ペーパーレス化によるワークスタイル変革に対応した預り物件管理業務の効率化を実現します。
- fcube CRMサービス
- 顧客情報の一元管理、金融機関向けコミュニティクラウド型CRMサービスです。
- 情報流通プラットフォームサービス事業
- インテックが提供するEDI関連サービスと、各種オプション/サポートメニューを紹介しています。
- EDIプラットフォームサービス
- インテック独自技術により、災害に強い「止まらないEDIサービス」を提供します。従来のEDI機能に加え、並列・分散・遠隔稼働を実現し、最上級のレジリエンスを実装しています。