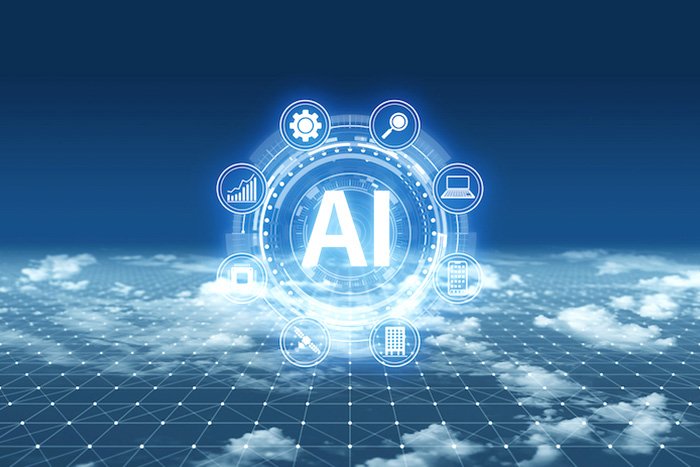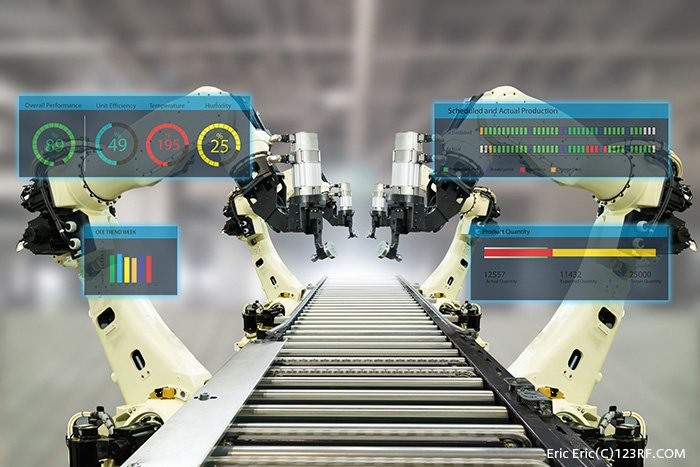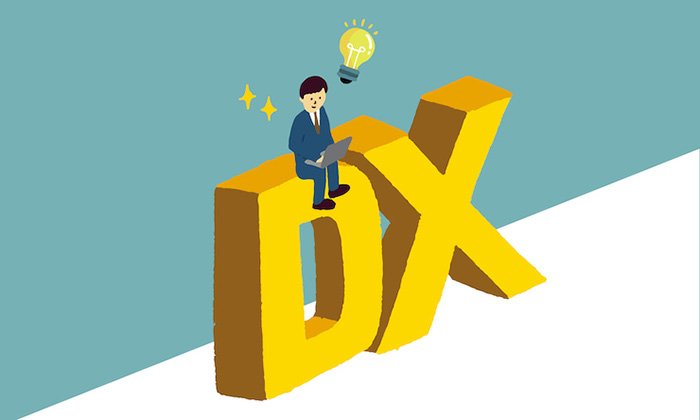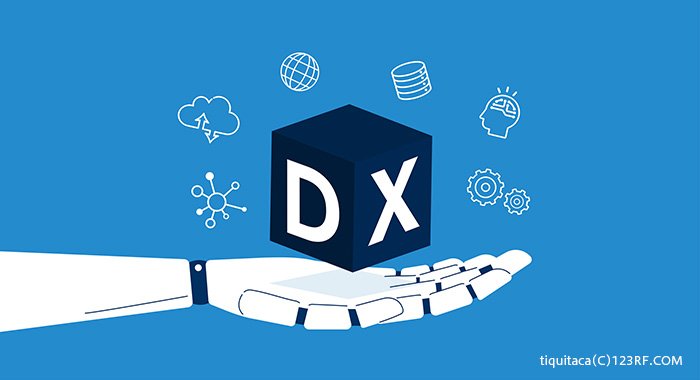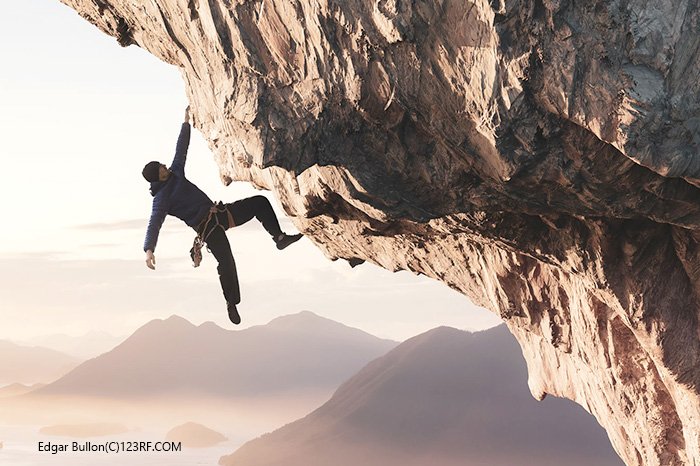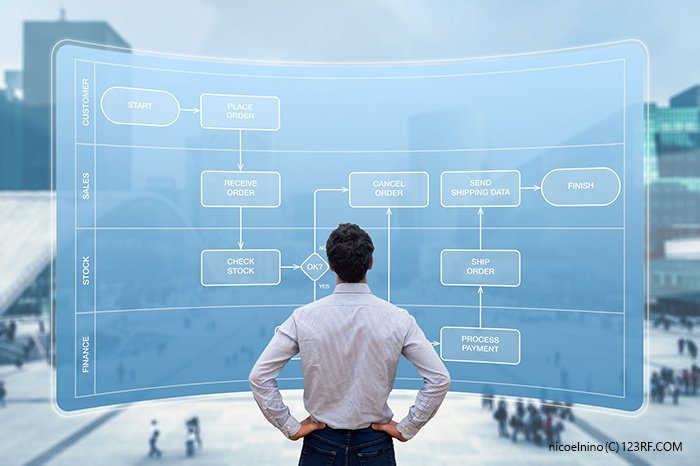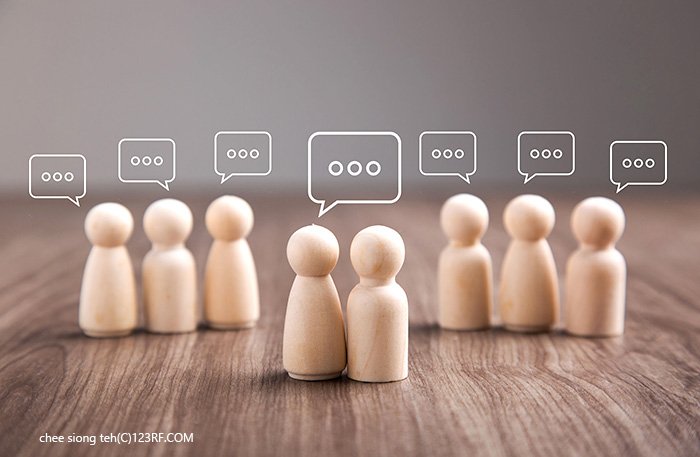【人流データの活用事例まとめ】自治体による地域課題の解決策を紹介

人流データとは、人の移動や滞在状況を数値で可視化するデータです。観光振興や都市計画、交通インフラなど、自治体や企業が抱える様々な課題を解決するために有効なツールとして注目を集めています。
一方で、「どのようにデータを活用するのかわからない」「自分たちの地域や組織でも本当に使えるのか」といった悩みや不安から、導入に踏み切れないご担当者様も多いのではないでしょうか。
本記事では、人流データの基本から実際の活用事例、導入時の注意点までをわかりやすく解説しています。地域課題の解決や効果的な政策立案を推進したい方は、ぜひご一読ください。
*スマートシティの実現に向けて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。
※その他のスマートシティ関連資料、お役立ち資料は<こちら>をご覧ください。
人流データ活用事例集の概要

人流データの活用事例を、国土交通省が発表する「人流データ利活用事例集 2025」より紹介します。この事例集は、全国の地方自治体における防災、観光、交通、まちづくりなど、様々な分野での人流データの活用事例が掲載されており、導入の背景や成果、課題まで紹介されています。
実践的なノウハウも学べるため、ぜひ参考にしてください。
人流データとは
人流データとは、人々がいつ、どこに、どのくらい集まり、どのように移動しているかの状況を、時系列や空間的な観点から把握できるデータです。主にスマートフォンの位置情報や交通ICカードの乗降履歴、各種センサーなど多様な情報源から収集されます。
このデータを効果的に活用することで、特定エリアへの人の流入・流出や混雑状況を可視化し、客観的なデータに基づく政策立案や公共サービスの最適化を実現できるようになります。
なお、人流データを用いた分析は、人流分析と呼ばれます。
データの種類や取得方法などの詳細については、こちら↓の記事もあわせてご覧ください。
関連記事人流分析とは?メリットやデータの種類、活用事例、導入課題を解
人流データ活用事例集の目的
人流データ利活用事例集の目的は、人流データの活用を広く普及させ、自治体が実際に導入へ踏み出すための第一歩を支援することです。事例集では主に、以下のような観点から具体的な事例を掲載しています。
- 具体的にどのような業務や分野に活用できるのか
- 費用や職員のスキル不足などの課題をどのように乗り越えたのか
- 小規模な自治体でも再現できる具体的なケーススタディであるか
特に、観光振興やまちづくりなど、多くの自治体で成果が出ている分野の事例が豊富です。
以下では、最新の事例を中心に、これまでの代表的な取組み事例からも厳選して紹介していきます。
観光振興に関する人流データ活用事例

ここでは実際に、人流データを活用して観光振興に取り組んだ自治体の事例を紹介します。
人流データは、観光振興を推進する上で欠かせないデータです。たとえば、観光客の動態把握や分析、観光施策の立案・実行など、幅広く役立てられます。
| 自治体 | 事業概要 | 活用した人流データ | 活用方法 |
|---|---|---|---|
| 山形県戸沢村 | 小規模自治体でもデータ収集・分析が可能な特徴を持つツールを活用し、観光分野での人流データ分析を実施 | スマートフォンアプリのGPSデータ | イベントや広告効果の測定に使用 |
| 長野県須坂市 | 須坂長野東インターチェンジ周辺の開発や新規ショッピングモール開業に伴う人の流れの変化を把握するため、人流データの活用を開始 | 観光地の来訪者数、イベント集客数などのデータ | 観光地の来訪者数把握、イベント効果測定、公共交通路線の検討などを実施 データは職員間で共有し、各部署が必要に応じて分析する体制を構築 |
| 北海道虻田郡倶知安町 | ニセコエリアの循環バスの運行期間の設定やルート検討、観光案内所の運営時間の決定、イベント実施時期の判断などに活用 | 宿泊データや先予約データ、観光案内所に設置した防犯カメラのデータ | 宿泊税データや観光統計と組み合わせることで、より正確な観光客の実態把握を実現 |
| 福岡県糸島市 | 観光地「二見ヶ浦」周辺や、その他の観光スポットにおける観光客の動向について、位置情報データに基づいた観光人流データ分析を行い、観光人流の見える化を実施 | 市内76ポイントのる観光客の位置情報データ | Yahoo!Japanの「DS.INSIGHT」や、市で独自調査している観光入込客数も併用し、観光客の動向を把握 |
1.山形県戸沢村|観光客の動向を人流データで可視化
山形県戸沢村では、総務省の「地域デジタル基盤活用推進事業」の支援を受けて、人流データを導入しました。戸沢村は、人口約4,000人の小規模な自治体です。サンプルが少なく、推計データの精度に不安がありました。
また、記録的な大雨による災害の影響を受けて、予算的な制約がありました。このような状況でありながらも、専門的な知識がなくてもデータの収集・分析ができるツールを採用し、工夫を凝らしています。
自治体の費用負担がない100%補助事業であることが、新しい取り組みにチャレンジする後押しとなりました。とりわけ、イベント開催時に施設への来訪者の動向を把握することで、広告による観光施策の効果測定・検証に人流データを活用する可能性を見出しました。
その結果、観光客の行動や広告効果を、具体的な数値として可視化できるようになっています。
2.長野県須坂市|観光地・動物園の来訪者分析
長野県須坂市では、観光地や動物園の来訪者状況を詳細に把握するために人流データを活用することで、観光施策の高度化に取り組んでいます。これまで感覚的に捉えていた事象も、データを活用して数値化・可視化することで、客観的な裏付けが得られ、政策立案や説明の説得力が大きく向上しました。
特に、観光戦略や集客策の検討では、来訪者数だけでなく、年代や居住地などの属性情報を把握できるようになりました。この結果、より的確なターゲット設定や今後の誘客戦略の立案に役立っています。
また、可視化されたデータは関係者間で共有できるため、合意形成やコミュニケーションの促進にも有効です。実際に人流データ導入によって職員間のコミュニケーションが活発になり、部署を越えた気づきや新たな分析の視点の提案が生まれるなど、組織横断的な議論も促進されました。
3.北海道虻田郡倶知安町|集客効果と観光動向を可視化
北海道虻田郡倶知安町では、観光庁の2020年度実証事業を契機として、ニセコエリアの観光施策の検討に人流データを活用しています。
たとえば、イベント開催時には各施設の集客数や来訪者の行動実態を分析して、施策の効果を数値で可視化しています。これにより、次年度の事業計画や予算要求の際に、データを根拠とした説得力のある説明が可能となりました。
また、町内のDMO(観光地域づくり法人)が中心となり、宿泊税の収入を自らの活動への補助金として活用し、データ活用を含めた観光施策の推進体制を構築しています。
人流データの分析からは、冬はインバウンド観光客が中心で、夏は日本人観光客が多いといった曜日ごとの来訪傾向も把握できました。関係者間でこれらのデータを共有することで、インバウンド観光客の平日利用も見込めるなどのインバウンド観光促進の意義に対する理解も深まりました。
4.福岡県糸島市|周遊分析と観光ルート最適化
福岡県糸島市では、九州大学との共同研究を通じて人流データを活用し、観光客の周遊パターンや観光地同士の連携可能性を分析しました。
具体的には、位置情報と検索データの取得を同時に実施しています。今までは、位置情報を把握できても、なぜそこに人が訪問するのかまでは解明できていませんでした。なぜその有名な施設に人が来るのか、どういった理由で何を求めて訪れているのかを調査するために、この分析の導入に至っています。
分析結果に基づき、観光協会が企画するバスツアーのルートを観光客の実際の行動に合わせたものへと最適化し、人気ツアーの開発につなげました。
また、データに基づく観光動向の把握により、観光客の嗜好にあったツアー設計や、観光客の困りごと(検索語)への先回り対応などが可能となりました。こうしたアプローチが糸島の観光まちづくりに大きく貢献することを実証できた点も重要な成果です。
都市計画・まちづくりに関する人流データ活用事例

ここでは、先進自治体による都市計画への具体的な活用事例を紹介します。
都市計画やまちづくりにおいて、人流データの活用は今や不可欠な手段となりつつあります。観光・商業施設の最適化、地域コミュニティや中心市街地の活性化などに役立てることが可能です。
| 自治体 | 事業概要 | 活用した人流データ | 活用方法 |
|---|---|---|---|
| 福島県郡山市 | 人流データ分析ツールを導入して、全庁的に人流データの活用ができる環境を用意 | スマートフォンのGPSデータ | 全行政センターの性別・年代・居住地ごとの来庁者数を把握し、可視化・分析 |
| 愛知県岡崎市 | スマート技術実装により楽しい・快適・安全なウォーカブルシティを構築 | 人流動線把握データ、通行人属性把握データ | 「one to many」「many to one」「many to many」でデータ利活用の事例の検討・構築・蓄積を推進 |
| 埼玉県さいたま市 | 人流データから求められる商業ニーズを分析し、駅周辺の不動産活用促進に繋げられるかを検証 | GPSにより取得した人流データ | 分析結果をもとに、不動産活用の阻害要因の特定と地域として今後とるべき施策について議論 |
| 愛媛県松山市 | レーザーセンサー(3D LiDAR)を用いて人の動きを定点観測することにより、移動軌跡として人流を取得 | 通過人数や移動経路などのデータ | 駅前広場整備の合意形成・計画策定のための検討材料として活用 |
| 広島県広島市 | まちなかの人の流れがわかるように、通行状況・滞在状況を可視化 | 通行量データとまちなか滞在データ | 中心市街地の人流データを可視化するダッシュボードを構築 |
1.福島県郡山市|行政運営と都市整備を効率化
福島県郡山市では、DX推進部署が中心となって人流データ分析ツールを導入し、全庁で活用できる体制を構築しました。
具体的には、市役所および市内14箇所の行政センターにおける年間来庁者数を分析して数値化し、各センターの所管業務の適正性を検証する基礎資料としました。さらに、行政手続きの受付件数や職員数などと組み合わせて活用することで、行政サービスの提供体制や人員配置の最適化を図りました。
また、道路整備の効果測定や公園再整備計画など、他分野でも人流データの活用が効果を発揮しています。
利用状況の把握もオンラインでデータ収集できるようになり、職員の業務負担軽減にもつながっています。
この取り組みは、DX推進部署が取りまとめ役となり、担当課とデータ活用のマッチングを実施した好事例として挙げられます。
2.愛知県岡崎市|通りのブランド化と歩きたくなる街づくり
愛知県岡崎市では、岡崎スマートコミュニティ推進協議会が中心となり、人流データを都市計画やまちづくりに積極的に活用しています。具体的には、ストリートごとの歩行者の流動特性を詳細に把握し、エリアごとに最適な業種の立地誘導や、通りのブランディング戦略に反映させています。
また、デベロッパーや商業事業者と連携し、人流データを活用したエリアの魅力を訴求する取り組みや、データの販売など、データ活用の可能性を広げてきました。
さらに、人流データは「ウォーカブルなまちづくり」の推進にも活用されています。ウォーカブルなまちづくりとは、誰もが居心地がよく、歩きたくなる空間づくりを目指す取り組みです
利用者の特性や利用実態に合わせた魅力的な空間形成・運用が期待されています。
3.埼玉県さいたま市|駅周辺の商業ニーズと不動産活用を分析
埼玉県さいたま市では、浦和美園駅周辺のまちづくりにおいて人流データを用いて、駅周辺の不動産活用促進につなげられるかを検証しています。
具体的には、駅周辺に求められる商業ニーズを分析し、市街地の環境変化も考慮した将来予測や不動産事業者等の地域関係者とのディスカッションを組み合わせて進めました。その結果、人流分析に基づく不動産課題解決施策の有効性が確認できました。
さらに、現在と将来にわたる商業ニーズをそれぞれ可視化したことで、賑わい機能の充実に必要な施策が明確となりました。これにより、今後の駅周辺まちづくりに関する建設的な議論へとつながっています。
人流データと関係者の意見を組み合わせた計画を策定することで、利用者ニーズに合致したまちづくりを実現した好事例として挙げられます。
4.愛媛県松山市|駅前歩行者動線を可視化し都市整備に活用
愛媛県松山市では、都市計画やまちづくりの精度向上に向けて、人流データ活用の実証実験に取り組んでいます。
具体的には、松山市駅前広場にレーザーセンサー(3D LiDAR)と呼ばれる高精度な計測機器を設置し、歩行者の移動軌跡を詳細に可視化しました。これにより、駅前のどのエリアに多くの人が集まり、どのルートを通って移動しているのかが客観的に把握できるようになりました。
また、市民やまちづくり関係者向けのワークショップでは、計測データを駅前広場整備の合意形成や計画策定の検討材料として活用しています。データに基づく議論によって、より精緻なまちづくりプランニングの実現が期待されています。
今後は、収集したデータを、将来像検討や都市整備計画への応用、立地適正化計画における施設や住居の高度化に向けた制度設計や客観的根拠としての活用していく予定です。
5.広島県広島市|中心市街地の活性化に活用
広島県広島市では「広島市DX推進計画」の一環として、中心市街地である紙屋町・八丁堀周辺の人流データの活用を進めています。
広島市DX推進計画は、市民・企業・地域団体などがデジタル技術を活用することで、新たな価値創造を目指し、持続可能な社会を実現するために、2022年3月に広島市が策定した計画です。
具体的には、人感センサーの設置やフリーWi-Fiの自動接続アプリから取得したアクセス情報をもとに、人の流れをリアルタイムで把握しています。これらのデータは、分かりやすく可視化したウェブダッシュボードとして一般公開されており、市民や事業者が自由に閲覧できるようになっています。
また、通行量データとまちなか滞在データは、ダッシュボードでの可視化だけでなく、オープンデータとしても提供されており、幅広い利活用が可能です。
今後は、まちづくり団体や商店街と連携しながら、地域活性化に向けた施策立案や事業の効果測定にも人流データを活用していく予定です。
交通に関する人流データ活用事例

ここでは、人流データを活用した交通分野における自治体の事例を紹介します。
交通分野の活用においては、混雑緩和や安全対策、公共交通の利便性向上など、住民サービスの質を高める上で効果的です。
| 自治体 | 事業概要 | 活用した人流データ | 活用方法 |
|---|---|---|---|
| 山口県宇部市 | 人流分析ツールを活用し、市内の主要施設(商業施設、病院等)への人の移動状況を分析 | 携帯電話の位置情報を基に推計したデータ | 主要施設を目的地として設定し、移動状況を分析 データ抽出は市職員が行い、分析は委託事業者が実施 |
| 福島県会津若松市 | データの重ね合わせ・可視化・分析により、持続可能な地域交通の構築に向けて、デマンドのあり方、交通計画見直しとの連動、周遊チケットの運用検討を実施 | 交通チケット利用者データ、施設利用データ、車内乗員データ、AIデマンド交通アプリの利用データ | 掛け合わせたデータを可視化・分析し、公共交通の再構築や新たなサービスの検討を行い、並行して動いている交通計画・再編策定事業と連携して活用 |
| 広島県東広島市 | モバイルGPSデータによる推定交通量と推定迂回路を利用した橋梁維持管理方針の検討 | モバイルGPSデータ、道路ネットワークデータ、橋梁データベース | 道路ネットワークデータとモバイルGPSデータを用いて各橋梁の推定交通量を算出するとともに、各橋梁の集約・撤去時に迂回路となり得る経路を推定 |
| 愛知県刈谷市 | 公共交通再編事業など3つの主要な事業で、それぞれの部署が人流データを活用 | Yahoo!データ、携帯端末の基地局データ、カメラの映像データ | Yahoo!データでコロナ禍前後の人流の変化を把握。 携帯端末の基地局データで市民の移動傾向を把握 カメラ設置によるデータ取得で、社会実験時の交通量や密度の変化を把握 |
1.山口県宇部市|市民移動を分析し公共交通改善に活用
山口県宇部市では、公共交通サービスの質の向上を目的に、市民の移動パターンを把握する取り組みを行っています。
具体的には、携帯電話の位置情報データを活用し、市内の主要施設における人々の移動パターンや混雑状況を分析しました。これにより、市民の移動状況についても、従来のアンケート調査では把握しきれなかった実態を、客観的なデータとして取得できるようになりました。
さらに、収集したデータは公共交通のサービス水準や利用実態の見直しに役立つ基礎資料として活用され、持続可能な交通インフラ整備の推進にも大きく貢献しています。
既に導入済みの人流分析ツールを活用することで、今後も同様の分析を職員自身で実施できる体制が整った点も大きな成果でした。
宇部市の事例は、データ活用による公共サービス改善の有効なアプローチとして、全国の自治体から注目を集めています。
2.福島県会津若松市|交通データ統合で公共交通とまちの移動最適化
福島県会津若松市では、地域の交通インフラ最適化に向けて、多様な人流データを統合しながら活用を進めています。具体的には、MaaS(Mobility as a Service)アプリなどから次のような人流データを取得して連携させています。
さらに、住基連動型GIS、携帯位置情報など人口データと掛け合わせた可視化、分析を実施しました。
- 交通チケットの利用データ
- 施設利用データ
- Bluetoothで取得した車内乗員データ
- AIデマンド交通アプリで取得したデータ
これらを公共交通の再構築や新サービスの検討に活かしています。交通計画・再編策定事業と連携することで、持続可能な地域交通の構築に向けた需要の把握や交通計画の見直し、周遊チケットの運用検討などに役立てています。
3.広島県東広島市|橋梁維持管理と優先度検討を効率化
広島県東広島市では、地域のインフラ維持管理に人流データを積極的に活用する取り組みを進めています。
市内には1,419橋の橋梁が存在し、すべての橋を維持・管理するための費用確保が大きな課題となっていました。そこで、広島県の「スタートアップ共同調達推進事業」を活用し、民間企業と連携して人流データによる調査分析を実施しました。
スタートアップ共同調達推進事業は、広島県内の市町が、革新的な技術・アイデアを有するスタートアップやベンチャー企業などをマッチングし、両者が協力をして地域や行政の課題の解決を目指す事業です。
具体的には、道路ネットワークのデータとモバイルGPSの情報を活用して、各橋梁の推定交通量を算出し、集約・撤去時に迂回路となり得る経路を推定しました。
また、橋梁の健全度や幅員・橋長、供用年度などの情報も考慮し、橋の統廃合や撤去、維持管理の候補選定や対応優先度の検討に役立てました。事前に想定していた撤去候補の橋梁について、データに基づく検証ができた点も大きな成果です。
4.愛知県刈谷市|移動データで公共交通再編と通路活用を最適化
愛知県刈谷市では、複数の部署が人流データの分析結果を行政計画や社会実験の検証に活用しています。
公共交通再編事業では、携帯端末の基地局データ(モバイル空間統計)を活用しています。これにより市民の移動傾向を把握し、地域公共交通計画へ反映させました。結果として、市民アンケートだけでは把握しにくい、小さい地域内での移動ニーズを可視化し、市バスの路線再編やデマンド交通の導入へとつなげました。
また、刈谷駅南北連絡通路活用における社会実験では、安全性の確認と効果測定を目的にカメラを設置し、人流を計測しています。データを可視化することで、施設管理者との協議も円滑に進み、実験範囲の段階的な拡大につながりました。
このような活用方法により、市民目線のサービス改善だけでなく、客観的なエビデンスに基づく効率的な施策決定にも寄与しています。
人材育成・組織構築に関する人流データ活用事例

ここでは、人流データを活用した人材育成・組織構築に関する自治体の事例を紹介します。
データ利活用やDXに興味があっても「ITリテラシーやデータリテラシーのある人材がいない」「組織全体に根付かない」と悩まれている方も少なくないでしょう。そこで、データの分析・利活用を担う人材の育成や、部門横断的な組織体制の構築に成功した事例を取り上げます。
| 自治体 | 事業概要 | 活用した人流データ | 活用方法 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横須賀市 | 人流データを全庁的に活用するため、政策部門による一括導入で、組織的な取り組みを実施 | スマートフォンの位置情報ビッグデータ | エリアや施設単位での来訪者数、来訪者の属性(年代・性別)、居住地などを分析 |
| 愛知県 | 観光デジタルマーケティングを推進するため、県と市町村が連携した人流データの活用を実施 | スマートフォンアプリの位置情報データ(おでかけウォッチャー) | 県が親アカウント、市町村が子アカウントという形で、同じ条件下でデータを共有・活用できる環境を整備 |
1.神奈川県横須賀市|全庁で人流データ活用を推進
神奈川県横須賀市では、全庁的な人流データの活用を推進するため、政策部門による一括導入で、組織的な取り組みを実施しています。
従来は、各部署が人流データ活用の必要性を認識していても、なかなか実践に至らない課題がありました。そこで、政策部門が主導となり、様々な行政分野で、マーケティング手法やデータを活用した政策立案や効果検証を「全庁的に」推進する体制を整えました。
また、各部署の自発的に活用を待つのではなく、政策部門が積極的に働きかけ、具体的なデータ活用方法の提案や、実践の伴走支援をしています。この仕組みによって、複数の部署において、地域や施設ごとの来訪者数や訪問者の年齢層・性別、居住地などの情報把握や分析が進み、データの利活用が進んでいます。
横須賀市のケースは、一部署にとどまらず全庁で人流データ活用を推進していくための実践的かつ効果的な成功事例です。
2.愛知県|市町村間で情報共有・事例を横展開
愛知県では、市町村も同じ条件でデータが活用可能な環境を整備したことで、市町村間の情報共有や事例の横展開が大きく進みました。
具体的には、市町村と連携して観光スポットの来訪者属性を分析し、ターゲットに応じた広告配信や新規事業の立案にデータを活用しました。実際に、データに基づく施策立案により、新規事業の立案に成功した市町村も出てきています。
また、研修会の開催や個別相談への対応など、市町村のデータ活用を支援する体制を構築しています。職員が自らデータ分析に取り組むことを重視し、実際の業務を通じて組織全体におけるデータ活用の能力向上を図っています。
こうした取り組みにより、特定の部署や担当者だけに頼らず、組織全体としてデータ活用能力を底上げできている点が特徴です。愛知県の事例は、自治体間連携と人材育成の両面から、人流データ活用の領域を広げた好事例として挙げられます。
インテックの人流データ活用事例・実績

インテックは、地域におけるデジタル変革(DX)推進を支援するため、人流データを活用したシステム構築やソリューション提供を行っています。
システム構築パートナーとして、幅広い知見と技術力を持ち、スマートシティ分野での実績も豊富です。特に維持費の課題に対しては、スモールスタートで地域の真のニーズを優先する姿勢がご利用者様から高く評価されています。
ここでは、これまでにインテックが手がけてきた人流データ活用の事例や実績を抜粋してご紹介します。
長野県伊那市|スマートシティと地域ブランド創出
インテックは、2023年5月に長野県伊那市と「新しいまちづくりに関する連携協定」を締結しました。「人や自然のぬくもりが確実に感じられる、伊那市独自のスマートシティ」を「Warm Smart City INA」と称し、伊那市らしいまちづくりと、地域ブランドの創出に向けた取り組みを進めています。
具体的には、地域の生活動態に着目し、若い世代に魅力的なまちづくりを行うことを目指して、市内3つの高校や公共交通拠点における人流データの解析を実施しました。取得データと地域データを組み合わせて、人の流れを可視化する実証実験を行っています。
また、2025年8月には、AIカメラを活用した駅の利用状況調査も共同で実施しています。高校再編による伊那新校や総合技術新校の開校を見据え、複数の駅の利用状況を詳細に分析し、利用ニーズに合った適正な施設整備を計画しています。
関連記事 新しいまちづくりに関する連携協定を締結 ~伊那市独自のスマートシティの構築、地域ブランドの創出に向け推進~
株式会社愛媛CATV|花火大会でAI解析による混雑緩和を実証
インテックは、愛媛県松山市で2023年・2024年に開催された三津浜花火大会において、株式会社愛媛CATVと連携し、混雑緩和を目的とした実証実験を実施しました。
三津浜花火大会は、例年約20万人が訪れる愛媛県内最大級の花火大会です。会場周辺および花火大会終了後の最寄り駅までの混雑における安全対策は大きな課題となっていました。
そこで、愛媛CATVが保有するデータセンターと地域閉域網を活用し、地域共同利用型の画像AI解析システムやデータ連携基盤を構築しています。
AIカメラとデータ連携基盤により、花火大会終了後の会場から最寄り駅間にある商店街の混雑状況をリアルタイムに測定・可視化しました。これにより、駅までの所要時間や到着時刻の予測、乗車可能な列車候補を通知できるかを検証しました。
2024年には、AIカメラの混雑検知の仕組みをより高度に活用しています。昨年の1.3倍という観客が訪れたにもかかわらず、帰宅者が集中する駅周辺区間の混雑状況は、2023年よりも緩和されたことが確認できました。
今回の実証実験を通じて、混雑検知技術や人流データが、イベント開催時の安全対策の施策検討に貢献できることが分かりました。
関連記事 インテックと愛媛CATV、三津浜花火大会で混雑検知の実証実験を実施 ~AIカメラとデータ連携基盤を活用し、検知技術・人流データの有効性を検証~
関連記事 愛媛CATVとインテック、三津浜花火大会で混雑緩和の実証実験を実施 ~時限付きクーポン活用や混雑可視化により来場者の行動変容を検証
株式会社秋田ケーブルテレビ|秋田竿燈まつりの安全管理とより良いまちづくりのための実証実験
インテックは株式会社秋田ケーブルテレビと連携し、日本を代表する夏祭り「秋田竿燈まつり」において、デジタル技術を活用した安全管理と運営の実証実験を実施しています。
秋田竿燈まつりは毎年8月に開催される東北三大祭りの一つです。4日間にわたり100万人以上が訪れる大規模なイベントとして知られています。会場周辺は歩行者の混雑解消(安全対策)を図るため、交通規制や臨時通路による横断対策などの対策が講じられています。
実証実験では、従来のライブ映像による状況確認に加え、AI画像解析技術による混雑状況の数値データを取得しました。これらのデータをもとに、混雑状況に合わせた安全管理業務への活用可能性を検証しています。
また、得られた人流データの活用は秋田竿燈まつりだけではありません。他の地域イベントや観光、地域事業者への情報サービスなどへ幅広い展開を予定しています。データの利活用による地域の持続的発展や地域経済の活性化につながる新たな施策やサービスの企画検討も予定しています。
*スマートシティの実現に向けて、こちら↓の資料もあわせてご覧ください。
※その他のスマートシティ関連資料、お役立ち資料は<こちら>をご覧ください。
人流データ活用の注意点

人流データの活用は、行政の意思決定やサービスの向上に役立ちますが、実際の導入や運用にあたってはいくつか注意すべき点があります。主なポイントは以下の通りです。
- プライバシー保護対策
- データの精度と分析スキル
- データ取得・運用のコスト
これらの点を押さえておくことで、人流データを安全かつ効果的に活用できるでしょう。
プライバシー保護対策
人流データ活用は、プライバシー保護対策が重要なポイントとなります。まず、個人を特定できないよう統計処理や匿名化技術を導入し、データ取得時にはその目的や利用範囲を明確に説明することが不可欠です。
また、信頼性を確保する上で、運用体制の整備と強固なセキュリティ対策を講じるとともに、第三者による監査体制を整えることも重要です。
法令を順守するだけでなく、住民説明会などによって事業の透明性を確保し、市民の理解と納得を得ながら事業を進める必要があります。
データの精度と分析スキル
人流データを行政施策に効果的に活用するためには、データの精度向上に加え、データを分析・解釈し、施策に落とし込むための専門的な分析スキルが求められます。
取得したデータに誤差や抜け漏れがあると、施策の方向性を誤るリスクが生じます。そのため、データの収集手法やサンプル数、分析環境は適切に選定することが重要です。
また、得られたデータを正しく読み解き、データから洞察を得て施策の裏付けとする能力が必要です。そして有効な知見として施策に反映させ、行動に移す実行力も不可欠です。
このような環境を整えるには、内部での人材育成に加え、外部の専門家や民間事業者と連携してスキルや知識を補完する体制づくりも、有効な選択肢となるでしょう。
データ取得・運用のコスト
データの取得やシステム運用にかかるコストを十分に考慮することも重要です。
センサーやIoT機器の設置、データの収集・蓄積・分析のためのシステム導入には、初期投資だけでなく、継続的なランニングコストも発生します。特に、規模の小さい自治体や企業では、これらの費用が大きな負担となり、データの収集が難しくなるケースも少なくありません
そのため、限られた予算の中で費用対効果を見極めながら、段階的な導入や外部サービスの活用、近隣自治体との共同運用など、コスト負担を抑える工夫も必要です。
まとめ:人流データを活用して地域DXを推進させよう
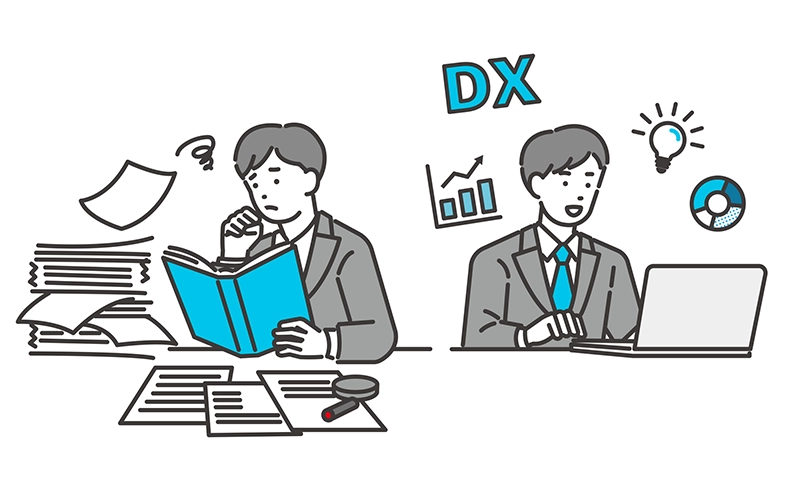
本記事では、人流データの活用について、事業分野ごとの先進的な自治体の取り組み事例を紹介しました。
人流データは、防災や交通、観光など行政や民間企業の様々な分野で活用が進んでおり、的確な現状把握と施策の精度向上に直結する強力なツールです。
インテックでは、創業以来、国や地方自治体の行政分野をはじめ、教育、医療、金融、メディア、産業など様々なビジネス分野で培った知見と実績を活かし、地域内の課題解決や魅力創出を支援してきました。
技術サービスの提供にとどまらず、導入前のコンサルティングや普及促進に向けたサービス創出支援まで実施しているのも特徴です。幅広い業務領域における現場の課題に合わせて、伴走しながら解決策を共に作り上げてきた共創型の事業支援によって、地域DXを推進しています。
人流データ活用に対する疑問や不安がある方は、「お問い合わせ」からぜひお気軽にご相談ください。
*インテックが提供する「DXに関する商品・サービス」または「エリアデータ利活用サービス」の詳細はこちら↓のページをご覧ください
サービス紹介 DXに関する商品・サービス
サービス紹介 エリアデータ利活用サービス
公開日 2025年10月16日
資料ダウンロード
-
【自治体の担当者必見!】失敗しない!スマートシティの進め方ガイドブック
本書はスマートシティの取り組みを推進するための進め方やコツについて解説するeBookです。 スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。

-
エリアデータ利活用サービス『事例集2025』『事例集2024』
2025年・2024年の事例集2冊をまとめてダウンロードしていただけます。
本書ではスマートシティの実現を目指すお客様に向けて、課題解決や取り組みに関する具体的な事例を多数紹介しています。スマートシティの取り組みを進める際の⼀助としてご活用ください。
-
エリアデータ利活用サービス紹介資料
スマートシティの実現を目指すお客様に向けて、データ連携基盤・都市OSの必要性やメリット、オープンデータの活用、各自治体での取り組み事例を紹介しております。
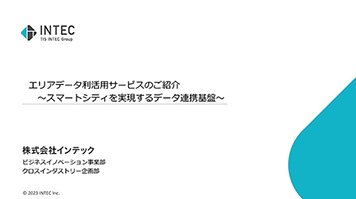
お問い合わせ
Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム
関連する商品・サービス
- エリアデータ利活用サービス
- IoTによるリアルタイムデータやオープンデータなど様々なサービス・ソリューションと連携し、地域の暮らしに関連するデータを収集・可視化・利活用を促進するデータ連携基盤を中心としたサービスです。
- ワイヤレスDXソリューション
- 広域仮想ネットワークサービスからマルチワイヤレス技術を用いて、ケーブルや端末、空間や場所などに制約のない環境を創出し、お客さまの課題解決を支援するソリューションです。