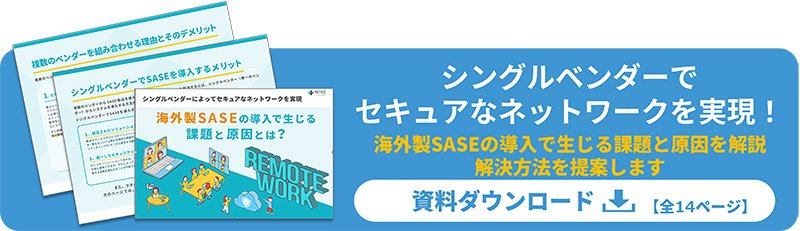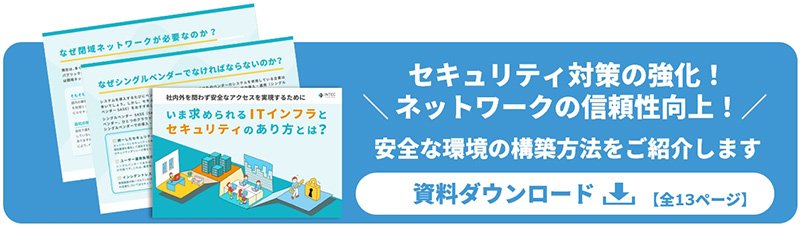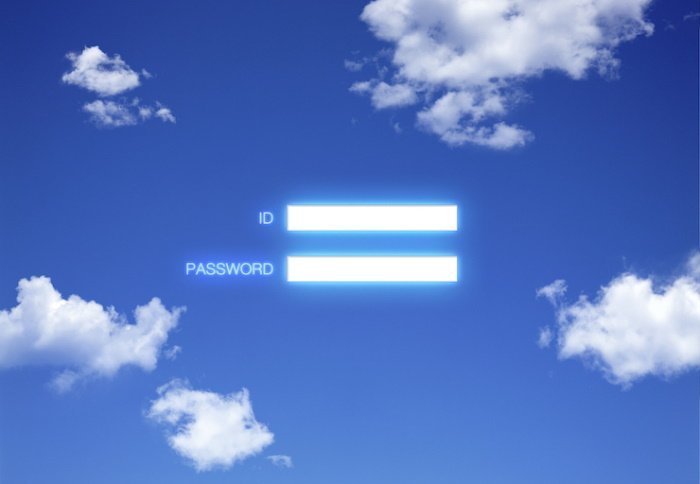いち早くIT-BCPの重要性を見通し、
ネットワークとシステムのワンストップ体制を提案
「EINS WAVE」でインテックが世に問うたもの

インテックが提供する「EINS WAVE(アインス ウェーブ)」は、広域仮想クラウドサービスからスタートし、お客様の声や社会の動向を取り入れながら成長してきた『SI+NI(システムインテグレーション+ネットワークインテグレーション)』サービスです。
その誕生の背景や、これから目指すビジョンについて、ICTプラットフォームサービス事業本部 ICTビジネス戦略部長に詳しく話を聞きました。
IT-BCPの未来を予見したことが「EINS WAVE」誕生のきっかけ
── まずはICTプラットフォームサービス事業本部と、ご担当の業務について教えてください。

ICTビジネス戦略部長
神保 岳大
ICTプラットフォームサービス事業本部はインフラ領域を専門に扱っており、データセンター事業、クラウドサービス事業、ネットワーク事業の3本柱で展開しています。なかでもネットワーク事業は、システム開発などを主とする事業者でありながら、クローズドネットワークやオープンネットワークなどの通信サービスも自社設備で提供しているという大きな特徴を持っています。
非常に広い領域を扱う事業本部なので、ビジネスの広げ方も高度なスキルが基礎になっています。私の所属するICTビジネス戦略部は、どういったお客様にどういった領域で提案していくか、各営業部門とコミュニケーションをとりながらプランニングしています。実際客先訪問して、先方の意向に沿うかたちでビジネス化していくといったところを担当しています。
商品カタログを見せながら、「このなかでご要望に合う商品はございますか?」といったやり方ではなく、社会の動向や私たちの成功事例を踏まえ、お客様とコミュニケーションをとります。お客様の会社や事業で課題となっている部分がないか、また先々課題となりそうな部分がないかを洗い出していくようなイメージです。ある種のコンサルティングと言ってもいいかもしれないですね。
また、現在提供している20種類ほどのサービスのなかには、単品パッケージとしてお客様にご利用いただける商品もあります。これをWebサイトやインサイドセールスといった非対面チャネルで提供するためのプロモーション施策も担当しています。
── 今回お話しいただく「EINS WAVE」には、データセンター、クラウド、ネットワークに加えてさまざまな業務システムなども含まれています。こうした、いわゆる「縦にも横にも広い」商品になったのにはどういった背景があるのでしょうか?
それは、2000年代後半に始まったデータセンターの拡充計画に端を発します。もともと、当社のデータセンターは東京都に開設されているのみでしたが、本社所在地の富山県にもデータセンターを開設する計画が進んでいました。その後、東日本大震災を経験してBCP対策のための需要も高まり、2011年には富山県に2か所のデータセンターを開設しました。さらに大阪府で、既存のデータセンター物件を借りる形式でのデータセンターも開設しました。
この計画時に、ICTプラットフォームサービス事業本部の責任者が考案したのが、各地のデータセンター間を高速ネットワークで接続して、仮想的に「ひとつの大きなデータセンター」として運用することです。システムを東京都のデータセンターと富山県のデータセンターに配置しておけば、東京都で万一のことがあった際にも、富山県のシステムで業務継続できると考えました。今でいうIT-BCP、ITにおけるビジネス継続性という考え方ですね。
2000年代の日本ではまだなじみのない考え方でしたが、当時の責任者は、前任部署でイギリスの通信事業について知見を深めていたのです。イギリスでは当時、すでにデータセンター間を高速接続していて、接続性も非常に自由で、お客様のITのシステム特性に応じて使うことがあたりまえになっていたそうです。そこで、「これは今後日本のITにおいても必要になるはずだ」と。
この考え方をもとにしてスタートしたサービスが「EINS WAVE」でした。つまり当初は、広域仮想クラウドサービスだったのです。
── そしてその後、サービス内容が広がっていったわけですね。
そうです。まずクラウド化や仮想化の技術が進展していくなかで、クラウドサービスを当社のデータセンター内に置いて、オンプレミスと同じように大容量のシステムを分散配置できる、もしくは相互バックアップのような考え方で管理できるというクラウドサービス、いわゆる後のIaaSを提供するようになりました。
また、東京・富山・大阪をつなぐ高速ネットワーク、いわば木の幹の部分は用意できていますので、その周りに、枝であるところのパブリッククラウドサービスとつなぐ機能を付けて活用していただく、という構想からのサービスも生まれました。
2010年代前半に出来上がったこの体制が、現在の「EINS WAVE」のデータセンター、クラウド、ネットワークの3本柱を形成する原型となっています。その後、組織変更でアプリケーションのチームと合流してからは、アプリケーションも当社のデータセンターに置いていたり、ネットサービスの先につながっていたりすることで、「EINS WAVE」の一部として提供するようになりました。
各スペシャリストの連携体制をワンストップで提供できる
── 広域仮想クラウドサービスや周辺のサービスをいち早く提供し、ノウハウを積まれたことは大きな強みだと思いますが、ほかにも「EINS WAVE」ならではの強みや特徴があれば教えてください。
われわれはデータセンター、クラウド、ネットワークというのはプラットフォーム、つまり、あくまで土台であると考えています。一般的に、この土台に乗せるもの、つまり、接続する業務システムは、お客様がそれぞれ違うベンダーと個別に契約したり、調達したりします。そうなると、お互いの責任分界点がありますし、そのせいでお客様側に負担が生じることも珍しくありません。
「EINS WAVE」では、この土台に、いくつもの業務システムが接続されています。具体的には、インテックで金融を担当している部門のシステム、自治体を担当している部門のシステム、医療を担当している部門のシステムなどです。つまり、土台から上に載るものまで全部まとめられるワンストップ体制になっているのです。
そうすると、例えば金融を担当している部門がCRMを提案するにあたって、顧客の金融機関から「システムコストを抑えたい」という相談があった際に、「うちには『EINS WAVE』がありますから、お客様側でインフラの運用管理をしなくても、アプリケーションを月額利用料制の、サブスクリプション形式でご提供できます」ということができます。
金融を担当している部門は、お客様から受ける業務オペレーションの質問に回答する、バッチ処理を行う、システムの自動処理を監視するといったことを担当します。われわれはネットワークがしっかりつながっているか、サーバー機器に異常はないかといったところを見ていきますから、それぞれの専門分野に合わせた役割分担が社内でできるわけです。今でこそあたりまえになりつつありますが、これを約8年前から提供していたわけですから、当時としては非常に斬新な考え方だったのではないでしょうか。
── 斬新な提案ができるということは、強みになりますね。
でも実は、われわれが新しいサービスを考えるきっかけは、「斬新なものをつくろう」という野心ではなく、「お客様の声」なのです。従来、お客様のシステムをデータセンターで預かっているケースが多かったからこそ、「EINS WAVE」のアイデアにつながるような要望が寄せられ、その結果として、斬新なサービスを提案するに至ったといいましょうか。
ともすると、「○○のようなことはできないの?」という要望に応えるかたちで、二番手、三番手として参じることにもなりかねません。しかし、それは先行しているサービスのフィードバック情報などを集めて反映し、よりよいサービスを提供できるチャンスでもあります。
オンライン旅行、超遠隔手術など通信インフラは想像を超える領域へ
── 今後この分野は、どのような方向に進んでいくと考えていますか。

これからさらに、高速・大容量・低遅延の方向へ向かうと思います。今、われわれの会話もお互いに届くまでにおそらく0.2~3秒のズレが生じていますが(取材はオンラインで実施)、こういったことが実は、さまざまなコミュニケーションの阻害要因になるのです。会話では意識しにくいですが、例えばオンラインで楽器を合奏する、動きをそろえてダンスをするとなると、やっぱりズレますよね。ただ現在のテクノロジーでは、ふたつの理由から高速・大容量・低遅延を推進するには限界があるともいわれています。
── 通信のタイムラグがなくなると、新たな可能性が生まれそうですね。しかし、なぜ限界があるのでしょうか?
理由のひとつは、通信が速くなっても、容量にリミットがあることです。つまり、画像や音声などのデータを決まった容量に収めるために圧縮して、送った先でまた復元するといった処理が挟まるので、遅延が生じてしまいます。しかも、圧縮してしまうと、復元してもオリジナルのクオリティにまでは戻りません。
これが、例えば現在の数百倍の容量で通信できるようになったら、圧縮せずにそのまま送れるようになりますよね。時間も遅れず、場所というか距離も超えて、どんなに遠く離れていても非常にリアルなやりとりができる時代がやってきます。そうなれば、応用領域は今よりも広がってくるでしょう。また、圧縮~復元の処理が不要になるということは、計算プロセスも大幅に減るということなので、さまざまなデバイスの消費電力削減にもつながります。
もうひとつの理由は、電気を使う半導体の性能がすでに物理学的な限界まで到達していることです。つまり、今以上の性能を出すためには、多くの半導体を並列につなげて数で稼ぐことになるので、消費電力や発熱が増えてしまうのです。電力といっても有限なリソースではありますし、環境問題を考えると発熱も望ましくないですよね。
こうした課題の解決策として、通信においてデバイスでも電気を使うことなく、すべて光で処理する「オールフォトニクスネットワーク」を主流にするべく、2030年ごろを目標に技術開発が進んでいるようです。これが世に出れば、想像もつかないような活用法が出てくるでしょうし、当然、業務で使うITの世界もガラッと変わるでしょう。テレワーク・リモートワークはもとより、旅行も現地まで行かずとも、オンラインで十分さまざまな体験ができるようになります。ロボットによる手術が進んで、離島にいる急病人を、ずっと離れた都市部の病院にいる医師が手術するといったケースも出てくるのではないでしょうか。
われわれも、お客様のご要望にいつでも応えることができるように、こうした新技術に追随できるよう、しっかりと投資をしていくことを基本に据えていくつもりです。
- ※本インタビューの内容は、2024年5月現在のものです。
- ※本文中の社名、製品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。
- ※本文中に記載されている事項の一部または全部を複写、改変、転載することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。
- ※本文中に記載されている事項は予告なく変更することがあります。
公開日 2024年07月04日
資料ダウンロード
-
海外製SASEの導入で生じる課題と原因とは
本書は、コロナ禍で海外製SASEを導入した企業が抱える課題と、その原因を明らかにしたうえで、有効な解決方法を提案します。
自社に最適なネットワーク環境を構築して運用の負担を軽減したいと考える、社内ネットワークの運用管理者やセキュリティ担当者は、ぜひご覧ください。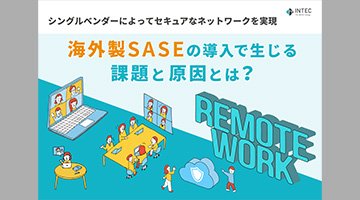
-
いま求められるITインフラとセキュリティのあり方とは?
本書は、デバイスを利用する場所を問わずに一貫したセキュリティ対策を実施し、同時に、業務に必要なITサービスへのアクセスを容易にする方法を紹介します。
セキュリティ対策について悩みを抱えている社内ITシステム担当者の皆さまは、ぜひご覧ください。
お問い合わせ
Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム
関連する商品・サービス
- EINS WAVE
- 共に課題解決するパートナーとして、お客さまのビジネスを支える最適なプラットフォームをスピーディーに提供したい。その理想をカタチにしました。
- EINS WAVE 統合型セキュアネットワークサービス
- お客さま拠点間やパブリッククラウドを快適に・セキュアに接続するマネージドネットワークサービスです。閉域網やオープンなネットワークを統合管理します。