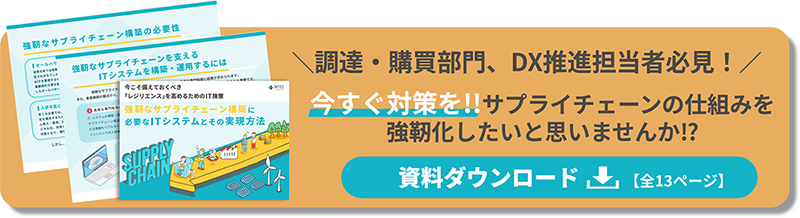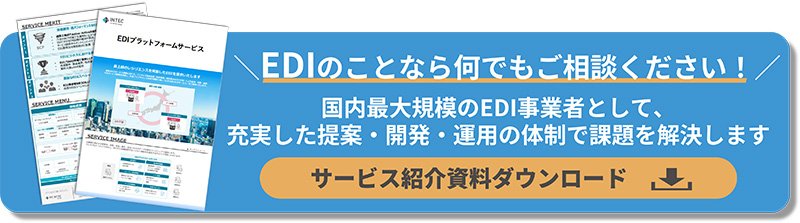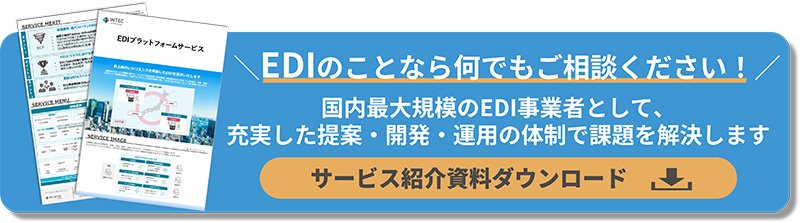流通BMSとは?JCA手順との違いや導入メリット、導入のポイントを解説
流通BMSとは?JCA手順との違いや導入メリット、導入のポイントを解説
流通BMSとは
流通BMSとは「流通ビジネスメッセージ標準(Business Message Standards)」の略で、流通業界全体の業務効率化・コスト削減を目指して導入された新たなEDIの標準仕様です。また、EDIとは「電子データ交換(Electronic Data Interchange)」のことで、企業間で電子データをやりとりすることそのものを指します。つまり、流通BMSとは、EDIのうち流通業界に特化した標準仕様を定めたものです。
*EDIについて、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
流通BMSとJCA手順
流通BMSの導入により、それまで使われていたJCA手順が順次置き換わっています。JCA手順と流通BMSの違いは以下のとおりです。
使用する回線
JCA手順は固定電話回線を利用していたため、通信速度が2400bps/9600bpsと非常に遅いものでした。一方、流通BMSではインターネット回線を使用するため、数Mbps〜数百Mbpsの速度を担保できます。これにより、JCA手順では1〜2時間かかっていた受発注業務を数十倍の速度で行えるようになりました。また、JCA手順では半二重通信という通信方式を採用していたため、一方が送信している間はもう一方が受信しかできないというデメリットがありましたが、インターネット回線を使用する流通BMSではその心配がありません。
専用モデム
半二重通信や固定電話回線の利用により、JCA手順では専用のモデムが必要です。しかし、流通BMSの普及に伴いJCA手順が徐々に使用されなくなり、専用モデムを生産している企業も減ってきています。そのため、壊れたときに新しいモデムが手に入りにくい状況です。一方、流通BMSはインターネットを利用するため専用モデムが必要ありません。
データ送受信内容の制限
JCA手順では送信できるデータが英数カナのテキストデータのみでしたが、流通BMSでは画像や漢字の送受信も可能になりました。これにより、データ送受信の幅がぐっと広がりました。また、JCA手順では1回に送信できるデータの大きさにも制限がありましたが、流通BMSではインターネット回線/XML形式になったことでより多くの情報の送受信が可能です。
*JCA手順について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
関連記事 JCA手順とは?流通BMSへの移行が迫られる流通業界のデータ送受信仕様
流通BMSとEDI 2024年問題
これまで流通業界の標準プロトコルであったJCA手順に代わり流通BMSが導入されるようになってきた背景として最も大きなものに、「EDI 2024年問題」があります。「EDI 2024年問題」とは、2024年1月にNTT東日本・西日本でINSネット(ディジタル通信モード)サービスが終了するというもので、これにより固定電話回線を使用しているJCA手順のようなレガシーEDIが、従来どおり使用できなくなるという問題のことです。
そこで流通業界で推奨されているのが、新たな標準仕様である流通BMSです。
*EDI 2024年問題について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
関連記事 INSネット(ディジタル通信モード)サービス終了への対策とは?EDI切り替え時の注意点を解説
流通BMSの導入メリット
流通BMSの導入により、以下のようなメリットが考えられます。
通信時間短縮、コスト削減
流通BMSの導入により、従来のJCA手順と比べて通信時間を大幅に削減できます。実際に通信時間を90%以上削減できたというデータもあります。通信時間が短縮できれば、出荷や検品業務の開始が早められ、業務がスムーズに進行できるでしょう。また、JCA手順専用に固定電話回線を使用していた場合、インターネット回線に統一することで通信費用の削減にもつながります。
メッセージフォーマットの統一
メッセージフォーマットがXMLに統一されたことで、企業ごとに異なっていたフォーマットが標準化されました。これにより小売店ごとに独自の仕様を持たなくなったため、卸やメーカーが新たな取引先を追加するたびにシステムを改修するという手間が大幅に削減されます。新規の取引先(小売店)を追加する際には、最低限の仕様を確認するだけで対応できます。
さらに、システムの開発期間や開発コストが大幅に削減されました。従来は、どの業務を対象とするか、やりとりするデータの仕様をどうするかなど細かい取り決めが必要でしたが、流通BMSで統一されたことにより、これらのすり合わせ作業を大幅に削減できます。
伝票発行や保管が不要に
流通BMSは税法上の取引記録として受領データを使用できるため、取引に際しての紙の伝票の発行や、それを保管する作業、保管するスペースが不要になります。紙の伝票には印刷コストや保管スペースの費用などさまざまな付随コストがかかるほか、紛失といったリスクもありましたが、流通BMSを利用することでこれらのコストやリスクを低減できます。
流通BMSを導入するうえで注意するポイント

流通BMSを導入するうえで、注意すべきポイントは以下の6つです。
サービスの違いに注意
流通BMSに対応したサービスとひと口に言っても、それぞれできることが異なります。例えば、小売業専用サービス、通信サービス、汎用(はんよう)サービスなどがあり、外部システムとの連携の可否、受注・出荷などの業務機能の有無などが異なります。それぞれの違いに注意し、自社に合ったサービスを導入しましょう。
セキュリティへの対応
流通BMSで規定されている通信プロトコルは、以下の3つです。
- JX手順...日本独自の通信プロトコルで、ほか2つよりも安価に導入・運用できる。主に中小企業が対象
- ebXML MS...国際基準の通信プロトコルで、近年アジア圏での利用が広まっている。主に大企業が対象
- EDIINT AS2...国際基準の通信プロトコルで、欧米を中心に普及している。主に大企業が対象
通信プロトコルは、取引先と同一のものを選択・導入する必要があります。そのため、利用するプロトコルは取引先と協議のうえ決定します。
XMLへの対応
流通BMSはメッセージの表現型式としてXMLを採用しているため、各メッセージのフォーマットがXMLスキーマで定義されています。XMLに対応していない業務アプリケーションがある場合、フォーマット変換機能を導入する必要があります。
インボイスへの対応
2023年10月からスタートするインボイス対応も、流通BMSに対応したサービスを選ぶ際のポイントです。これは流通BMS 基本形2.1に準拠したシステムで適用され、登録番号や返還インボイス、保存義務などに対応しなければなりません。
*電子インボイスについて、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
関連記事 電子インボイスとは?基本知識やメリット・デメリット、ペポルについて解説
流通BMSはメリットが多いが、ポイントに注意して導入しよう
流通BMSは、これまで使用されていたJCA手順に代わって導入が進むEDI標準のひとつです。流通BMSの導入により、通信速度の大幅な向上やメッセージフォーマットの統一、そして紙の伝票の発行や保管が不要になるなど、多くのメリットがあります。一方で、流通BMSの導入にあたってはEDIを再構築する必要があることから、今回ご紹介したようにポイントを押さえて行う必要があります。
インテックのEDIプラットフォームサービスでは、流通BMSのようなINSネット(ディジタル通信モード)のサービス終了に対応したEDIの導入から運用までをアウトソーシングでき、コストや手間を削減できます。EDIの構築だけでなく、運用もアウトソーシングできるため、煩雑化する業務運用のためにリソースを削減することなく、コア業務に集中できるでしょう。
流通BMSの導入を検討される際には、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
*INTECが提供する「EDIプラットフォームサービス」の詳細はこちらのページをご覧ください
EDIプラットフォームサービス公開日 2023年03月20日
資料ダウンロード
-
「強靭なサプライチェーン構築」ホワイトペーパーのダウンロード
強靭なサプライチェーンの構築は、現代のビジネス環境において、事業継続性を確保し、競争力を維持・向上させるための不可欠な要素となっています。自然災害の増加やサイバー攻撃の脅威、さらには人手不足といった課題に直面する中、企業はサプライチェーンの強化を急ぐ必要があります。
本書を通じて、強靭なサプライチェーンを支えるITシステムの重要性と、その構築・運用における課題を明らかにし、システム及び業務停止リスクの回避および業務効率化を実現する方法を提案します。
-
EDIプラットフォームサービス 紹介リーフレット
EDIプラットフォームサービスは、企業間で発生する受発注、出荷、返品、請求、支払いなどのデータ交換をワンストップで実現します。また、「遠隔、分散、並列」の環境にて、最上級のレジリエンスを標準性能として提供いたします。サービス概要を記載しておりますので、ぜひ、以下よりダウンロードしてください。

-
【動画】もう待てない!外国送金ISO20022対応とEDI基盤の真のBCP対策とは~期限迫るサプライチェーンDXの課題を徹底解説~
2025年11月に期限が迫るISO20022移行に関する課題や対策についてご説明いたします。
また、対応ソリューションについてご紹介いたします。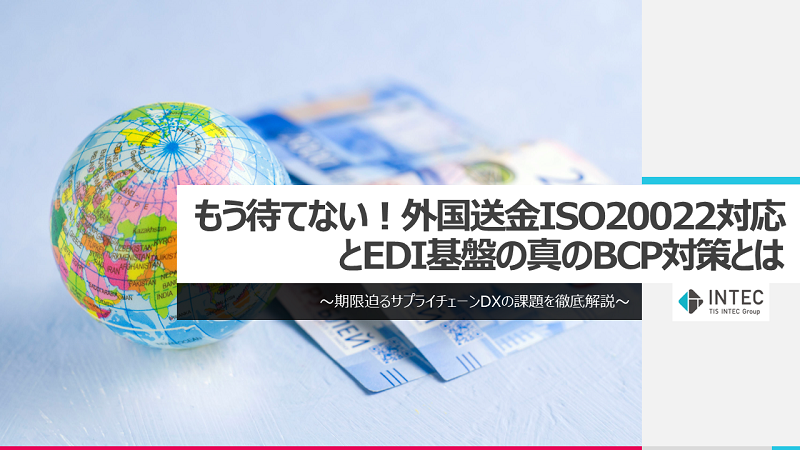
お問い合わせ
Webから問い合わせるあわせて読まれているコラム
関連する商品・サービス
- EDIプラットフォームサービス
- インテック独自技術により、災害に強い「止まらないEDIサービス」を提供します。従来のEDI機能に加え、並列・分散・遠隔稼働を実現し、最上級のレジリエンスを実装しています。
- 情報流通プラットフォームサービス事業
- インテックが提供するEDI関連サービスと、各種オプション/サポートメニューを紹介しています。