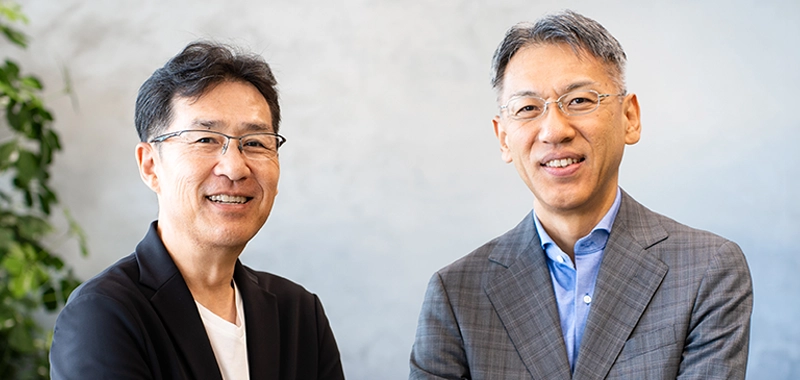1988年の同期入社だが2012年まで
ほとんど話をしたことがなかった
── お2人とも、ほぼインテック創業時に生まれ、1988年に同期入社しています。当時インテックを就職先に選んだ理由と、入社後の経歴をお願いします。

眞門:
私は1988年にインテックに入社しました。大学は経済学部で、同期のほとんどは金融機関に就職しましたが、私自身はあえて違うところへ行ってみたいという気持ちがあり、富山県出身ということもあってインテックを選択しました。当時の新人は必ずシステムエンジニア(SE)の経験を積むことになっていましたので、プログラム作成を中心に東京でSEを3年やった後、本社の財務部門へ異動しています。途中、1年半ぐらい人事部にいましたが、ほぼ財務畑一筋で、資金調達するための金融機関との取引や、社債の発行など、仕事内容は事業そのものとは離れたかなり特殊なものでした。
2012年に東京へ転勤となり、経営管理部へ異動しました。これまでは財務会計が中心でしたので、管理会計のことはほとんどわかっておらず、自分の概念にない仕組みで会社が動いていることを初めて知り、相当のギャップを感じたことを覚えています。

疋田:
私は大学が理系だったのですが、業界を絞らず就職活動をし、数社受けたうちの1つがインテックでした。内定もいくつかいただきましたが、全ての会社のOBとお会いして話を伺い、その印象で決めたのがインテックです。
入社は眞門と同じ1988年で営業職を希望していましたが、大阪でシステム課へ配属されました。ただ配属後すぐにお客さま先へ常駐することになり、そこのインテック営業担当が就職活動の時に話を伺ったOBの方だったというご縁で、営業職になるまでにいろいろと勉強させてもらいました。
3年目にようやく営業職に変わり、以来20年間大阪で勤めてきましたが、2012年に東京転勤となり、これまで全く経験のないインフラ事業の総責任者という立場となりました。技術責任者のプレッシャーもありましたが、若手社員に教えてもらったりしながら勉強する毎日で、私にとって1つの転機になったと思っています。その後、首都圏の営業部門にも配属され、多くの経験をさせてもらいました。
眞門とは同期入社と言っても、当時350人ぐらい採用していたので、2012年に東京へ転勤になるまでは、全く接点がなかったと思います。厳密に言うと、2012年より前に当時の会長の社員教育塾があり、そこで一緒になっているはずですが……。
眞門: 2012年に東京へ同時に異動になったとき、先輩社員が食事会をセッティングして、そこでじっくり話をしたのが最初だと思います。そのとき、所属員全員と面談したという話を聞いて、すごく熱い人だなと感じた記憶があります。
疋田: やっぱり「大阪から急に来た営業?どんな人?」と思われるのも嫌だったので、東京のメンバーと交流を深めたいという思いから全員と面談しました。
── これまで携わってきた仕事の中で印象に残っていることはありますか。
眞門: 財務中心の仕事の中で印象に残っていることは、社債の発行など教科書にしか書かれていないようなことに、自分が携われたことですね。よい経験になったと思っています。
疋田: 私はほとんどを営業職として過ごしてきましたが、お客さまの懐に入って深い関係を作るという思いでずっとやってきました。今でこそ異なる立場や業界の企業・団体が協力して、新たな商品・サービスや価値観などをつくり出す“共創”という言葉を使いますが、2000年代前半は一般的ではありませんでした。そんな時代にお客さまと一緒に会社を立ち上げる企画から、システム開発の運営までを一緒にやらせていただく機会があり、その経験は非常に勉強になり、思い入れもありますね。今もその会社とは取引が続いています。立ち上げた当時の方はすでに引退されていますが、今回社長就任発表の際もいちばんにお電話をいただき、人生のなかでもいい出会いと経験を積めたと思っています。
── 仕事以外のプライベートな時間はどのように過ごすことが多いですか。
眞門: 今こうして2人で話をしていますが、入社後の道のりが全く異なるので、お互いのプライベートの部分はあまり知らないんですよね。
疋田: おそらく、2人ともほかの人から見たら仕事大好き人間に見られていると思います。私は休みの日はお客さまとのお付き合いのほか、ランニングや学生時代にやっていたラグビーの観戦、バンド活動などでオフの時間を作るようにしています。
眞門: 私は若い頃はスキーやサイクリングをしていましたが、5年ほど前から書家の森大衛先生の教室に通うようになり、毎年展覧会に出すようにしています。今回も色紙を書いてきました。書道をする時間は集中しているので、仕事のことを忘れられる機会にもなります。
想像以上の忙しさに
手分けをして対応していきたい
── 就任にあたって、率直な感想や思いをお願いします。
疋田:
今回代表取締役社長という立場に就きましたが、昨年度は副社長をやっていましたから、社長がどういう仕事をしているのかを身近で見る機会が多くありました。ただ、いざ社長になってみると「こんなに忙しいんや」というのが正直なところです。寝ても覚めても仕事のことが頭を巡っています(笑)。
当然ながら、経営として会社全体のことを考えないといけませんから、コーポレートの仕事も全て入ってきます。そこは今まで私自身が見えていなかったところも非常に多いと感じました。中期経営計画を考える際にも、人事や企画、総務の仕事も奥が深いところが多いと非常に感じるので、日々勉強ですね(笑)。眞門とは、ここに来るまでの経歴が違いますし、それぞれの持っている知見を活かして補完し合おうという話を最初にしました。
眞門: 私の副社長という立場は昨年度と変わらないのですが、他社の社外取締役に就く機会をいただき、外部の方と話す機会が増えたり、6月には社員といろいろな話をする機会を設けたりして、昨年とはだいぶ違う感覚です。これまで歴代社長に仕えてきて、疋田で5人目になりますが、社長の時間を作るというのは、ある意味大事なことだと思っています。本来我々で受けるべきことを社長にやらせてしまっていることが多く、何でも社長に決めてもらうのではなく、しっかり計画を立て、こうしていくと示すところまでやらなければならないと思っています。
疋田: 眞門にももっと外に出て副社長の顔を売ってほしいですね。私の身体は1つなので、全国を回るとなると参加できないものがたくさんあります。手分けして参加するためにも、もっと外に顔を売っていく必要があると思っています。
右肩上がりの状況を続けていくために
全社一体となって突き進む
── 中期経営計画(2021~2023)の目標をおおむね達成した状態で引き継ぎました。ここからさらに右肩上がりの業績を築いていくというプレッシャーはありますか。
眞門: 現在、おかげさまで会社は好調であると思っています。中期経営目標をおおむね達成し、それを維持しつつちょっとでも伸ばそうというのは、今までと同じことをやっていても無理だろうと、昨年1年間いろいろと頭を捻ってきました。すごくプレッシャーを感じていますが、1人で解決するわけではないので、チーム一丸となってやっていきたいと思っています。
疋田:
プレッシャーがないと言ったら嘘になりますが、業績はやはり右肩上がりで伸ばしていくのは当然のことだと思っています。眞門が言うように、今までと同じやり方では非常に難しいですし、今の社会の関心は働き方のさらなる変革、高齢化、生産労働人口の減少であり、つまりはSE不足になるのが見えているわけです。
そういったことも踏まえながら、どうやって会社としての一体感を作っていくのか、今までにない難しさが我々の目の前に立ちはだかっている印象です。
富山から発祥し、独自のサービスを作ってきたというプライドがインテックのDNAだと思っています。そこの軸を持っている社員は非常に多いと感じていますが、若手社員にもそのDNAを伝えていく必要があると思います。
眞門: 昔から続いているスポーツ大会などのイベントを継続していたり、社員同士で仲がよいのはインテックのいいところだと思います。そういう部分はこれからも残していかなければならないですし、それが強みになっていると思っています。どんな優秀な社員がいても、仲が悪ければうまく回りませんからね。
疋田: 次の高い目標を全員で達成するためには、今までと同じやり方ではなく、1人1人が変わっていこうとする意識改革が必要です。会社の一体感の醸成や社員同士の交流を深めることが、意識改革のエネルギーになっていくと思います。
第20次中期経営計画の
方針に込めた思いとは
── 第20次中期経営計画が発表されましたが、今回は3年後のありたい姿を示しています。
疋田:
これまでも新中期経営計画の発表において、その時の情勢を鑑みた基本方針を掲げていますが、3年後のありたい姿を中期計画の初年度に示すということは、今回が初めてだと思います。ITによる無限の可能性の探求は感動を生み出すことができると思うので、そんな未来を我々で形成していきたいと考えています。それをお客さま、あるいはステークホルダーと”協奏“する。共創を超えて協力しながら奏でる、そういう会社を目指していきます。
インテックは創業から「技術立社であれ」と言われています。プライドを高く保ち、培ってきたノウハウ、新たな技術を取り入れて、当社独自の唯一無二な技術やサービスを世の中に出していく。今は技術の進化も速いので、それを実現することは、大きなチャレンジだと思っています。さまざまな制約や困難はありますが、チャレンジしていくからこそ、そこには感動が生まれて、社員の活力そのものになると考えています。
感動をみんなで共感できるようになってくれれば、さらなるエネルギーが生まれ、好循環となってより成長ができるということを、社員には伝えています。
眞門: 社長の思いをいかに成し遂げられるか。ライン部門とコーポレート部門がうまく一体感を持って進めていきたいと思っています。それは第20次中期経営計画の基盤の部分であり、さまざまな取り組みを行っています。そういった面をしっかりやって、中期経営計画のありたい姿を成し遂げていくことに貢献していこうと思っています。
── 急速的に発展するテクノロジーに対して、どのような取り組みをしていこうと考えているのでしょう。
疋田: 例えば生成AIについては文章生成をするだけではなく、我々のインテグレーションの技術の中で、どこに適用させればより生産性が高くなるのかまで追究しなければならないと考えています。それらを担うため、この4月に新しく技術戦略本部を立ち上げました。どこにどういう技術を適用させるかというのは非常に複雑で難しく、逆に言えば、そういうノウハウがあるから我々の存在意義がありますし、価値があると思います。我々エンジニアが、より高度にレベルアップ、バリューアップをして、価値を追求し続ける必要があります。
眞門: この3年間は、収益を上げることを中心にやってきました。その結果ここまで来られたわけですが、今後はAIを使ったり、いろんな技術を使ったりして生産性を上げていくことが必要です。お客さまへ提供するサービスの価値を高めるのは大変なことですが、実現するべく組織変革を進めていきます。
これからのインテックが
目指すところ
── 創業60年を迎え、これから70年、100年と突き進んでいくために、インテックが目指すところやこれから期待してほしいことをお願いします。
疋田:
100年企業を目指すにあたり、その時代の変化に合わせて変えていかなければならないところ、変えてはならないところがあると思っています。IT分野の技術進歩は速いので、これにどうやって順応していくかが非常に難しい時代になってきています。とはいえ、これまでの仕事が一気に変わることはありません。TISインテックグループのプライドとして品質をきっちり担保し、お客さまに安心・安全を提供していくことが根底にあります。
単に商材を仕入れてお客さまにお納めするのではなく、そこに最適な技術を取り入れ、独自のサービスとして提供していく。しかもそれを特定のお客さまだけではなく汎用的なサービスで提供するということをずっとやってきました。お客さまからは常に新しいサービスを要求されますから、汎用的なサービス基盤を作り上げるという考えは崩さず、常に進化させていく必要があると思っています。
ただ、新しい技術がものすごい勢いで出てきているのも事実で、そのためにニーズも多様化しています。若い人たちはこうした尖ったところへ行きたがりますが、やはり支えになるのはベース開発スキルなので、それを怠ってはいけないと思います。人材に対する投資は今後もしっかりとやっていくので、学習の積み重ねを成長の糧にしてほしいと思います。
眞門:
我々は、どちらかというと社会基盤的な事業をやらせていただいています。新しいことも大事ですが、安心、安全がきちんと担保されている必要があります。とはいえ、新たなものを取り入れることも重要で、積極的に投資していくことも考えています。自分の担当に目を向けると、コンプライアンスという部分も非常に大きく、時代の変化とともに社会の要請も変化していくので、より良いものを目指して社内の体制も変えていく必要があると考えています。社内での情報共有も非常に大事なので、しっかりと活性化させ、前向きな形で対応できるよう変えていきたいと思っています。
もう1つ、インテックは富山発祥であり、富山の皆さまのおかげで会社が設立され、さらには事業を拡大することもできました。日本のグローバル企業には、東京に本社を置かず発祥の地のままにしているところも多く、大きくなる企業は原点を大事にしているという共通点があると思っています。全てのお客さまに感謝し大切にするのはもちろん大事なことですが、原点である発祥の地に対する思いは、これからも大事にしていきたいと考えています。